
薩摩藩の郷中教育によって政治家として活躍する素地を形作った大久保利通(第1回)。21歳のときに父が島流しになり、貧苦にあえいだ(第2回)が、処分が解かれると、急逝した薩摩藩主・島津斉彬の弟、久光に取り入り(第3回)、島流しにあっていた西郷隆盛が戻ってこられるように説得、実現させた(第4回、第5回)。
「身の程知らず」だった薩摩藩
「身の程知らず」という言葉を、筆者はどうにも好きになれない。自分の身の丈以上のことをせずして、いかにして事を成せるというのだろうか。
大久保利通の同志である西郷隆盛は、島津久光に「あなたはジゴロ(田舎者)だから」と暴言を吐いて上洛計画に異を唱え、結果的には島流しになっている。「無位無官の久光が京に上ったとて、自分が敬愛する斉彬の代わりはできない」というのが、西郷の本意だった。
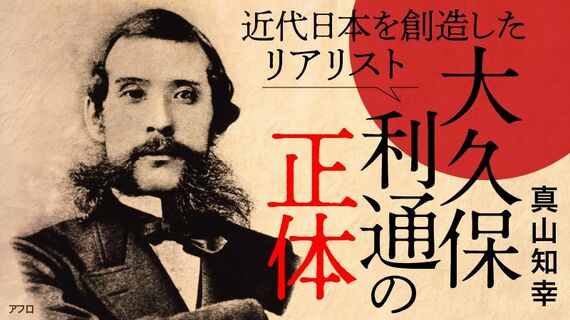
つまりは、「身の程を知れ」ということだが、西郷はもちろん、斉彬とて中央からみれば藩主だろうが、身の程知らずの「ジゴロ」あることには変わりない。
いや、というよりも、外様でありながら、中央政治に影響力を持とうとした薩摩藩全体が「身の程知らず」だといえよう。
その先駆けともいえるのが、8代藩主の島津重豪だ。11代藩主の斉彬にとっては曽祖父にあたる人物である。

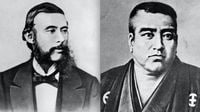
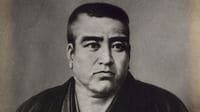






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら