
「買い替える」のが当たり前の社会
前回まで、「使い捨て」と手を切ったことでスルリと手に入れたわが「心安らかな人生」について滔々と語ってきたわけですが、ま、改めて考えてみればこんな発想は今ドキ特に珍しいというわけではなかろう。
ある日の新聞を見れば、私から見れば使い捨て社会の主要メンバーにも思えるコンビニ各社ですら、使い捨てプラからの脱却を図っているそうである。
プラスチックのストローとかフォークとかスプーンとかを、植物性由来の素材を配合したり、軽量化したり、一部の店では木製にしたりすることで、使用するプラスチックの量を減らしているそうな……いやね、大変申し訳ないが、そもそもストローもフォークも使わない(飲み物は容器から直接飲むし、何かを食べるときは箸一択)私としては「手ぬるい」感じがしないわけではない。
とはいえ、今や現代日本文化の象徴とも言えるコンビニの影響力を考えればやらないよりやったほうがずっといいことには違いなく、その決断に敬意を表するとともに、さらなる進化を心より期待したいところであります。
それはさておき。
今回は「使い捨て」ということについて、もう少し突っ込んだ話を書かせていただきたく思う。

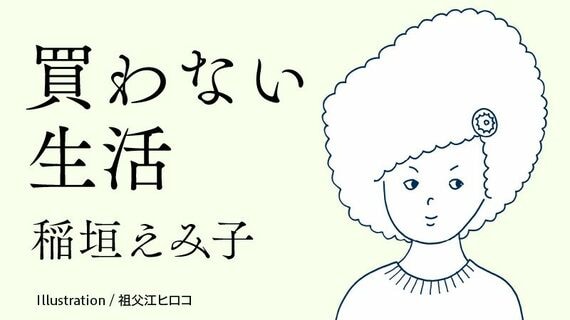






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら