
「不動産業者からの電話は毎日ですね。だいたい家賃滞納やトラブルの知らせです」
認定NPO法人「自立生活サポートセンターもやい」理事長の大西連氏は、個人でおよそ1300世帯の緊急連絡先を引き受けている。このため知らない番号から、頻繁に電話がかかってくる。
もやいでは住まいを失い、社会から孤立する人々をつなぐ活動を行っている。2000年代初頭、日雇い労働者を中心にホームレス状態の人が急増した。公的なシェルターに入っても、アパートを借りる際の「連帯保証人」の壁に阻まれ、自立への道を閉ざされる人が後を絶たなかった。この問題を解決するために、支援団体が集まってもやいが2001年に設立された。
連帯保証人を引き受ける中で、利用者の事故率は約5%だ。意外に低いかと思いきや、通常は1%以下のためリスクは5倍超である。
滞納補填や孤独死した部屋の片付けなど、年間で数百万円の費用が発生する。トラブルを抱えた支援者ともやいが訴えられて、裁判を抱えることもある。
コロナ禍で増えた貧困支援
現在の活動内容は、食料支援、相談事業、孤立を防ぐ居場所の提供へと広がっている。さらには、身寄りのない利用者が亡くなった後の葬送も手がけ、共同墓地への受け入れまで行っている。
東京では行政に委ねても民間の斎場に個別に委託されるため、遺骨の納骨先がわからなくなってしまうケースが少なくない。生前に関わりのあった人々が「お墓参りをしたくてもできない」という現実があった。このため本人の意思を尊重して無宗派の寺院へ納骨しており、これまで70名を埋葬してきたという。
食料支援では、毎週土曜に都庁前で食料配布会を行う。野宿者を中心に当初100人程度だった利用者は、コロナ禍の2020年から目に見えて増えていった。
今年6月には840人が列に並び、家や仕事があっても生活が苦しい人、年金生活をしている人、子連れの家族の姿も増えた。「物価高の影響もあり、多くの人々の生活が苦しくなってきている」と大西氏は指摘する。

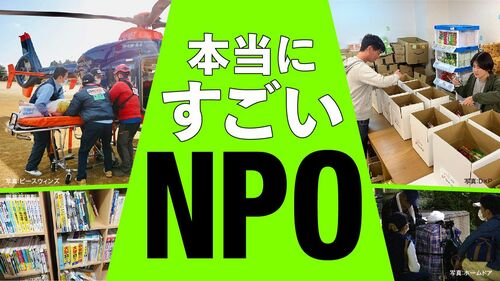
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら