食糧支援の年間配布量は100トンに及ぶ。企業から寄付された食品や野菜、物資を1人分ずつスタッフが手作業で準備して配布している。
相談事業では、メール・電話・チャット・対面で窓口を設け、住まいの問題に限らず、日常のあらゆる困りごとに無料で応じている。
当初は野宿状態の生活を送っていた相談者が中心だったが、今ではシングルマザーや障害者などさまざまな背景を持つ人へと対象が広がり、2023年度には年間3800件もの相談が寄せられた。
孤立を防ぐための居場所づくりとして、月3回は「サロン・ド・カフェこもれび」も運営する。350円で食事と飲み物を提供し、当事者自身がコーヒーの焙煎や運営に関わることで、社会参加への小さな一歩としている。
もやいは支援の対象者を絞っていない。「いろいろな人が来られることを団体のポリシーにしている」(大西氏)からだ。
相談者のプライバシーを守る
活動を支える原資は、94.6%が個人からの寄付で成り立っている(2023年度)。コロナ禍以降、社会課題への関心の高まりとともに寄付額は1億円を超えるまでになったが、その道のりは常に不安定だった。

メディアで大きく注目されたリーマンショック後には寄付が急増したものの翌年には半減し、東日本大震災の年には国内の支援が被災地に集中したことで、運営は赤字に陥ったという。
企業からの金銭的な支援は少ない。大西氏は「子ども支援などに比べ、貧困というテーマは企業イメージにつなげにくい側面がある。何より私たちの活動は、相談者のプライバシーと尊厳を守ることが大前提」という。
大人の貧困が抱える問題はさまざまだ。支援現場でカメラを回すと来づらくなる人もいれば、過酷な状況を切り取って発信すれば「自分はまだ相談するレベルではない」と萎縮して支援から遠ざかってしまう人もいる。

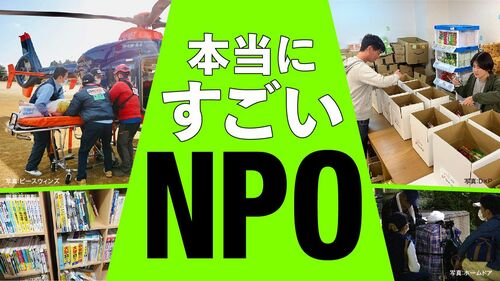
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら