異色の国内最大NGO「生みの親は外務省と経団連」→官と民をつないで加盟NGO47団体へ助成金・寄付金を分配、被災時は現地調査員が緊急対応

国内外の大規模災害や、ガザやウクライナなど人道危機の現場で困難に直面する人々を支援する、NGOや支援団体。その彼らの活動を、裏方として支える組織がある。認定NPO法人ジャパン・プラットフォーム(JPF)だ。
JPFには、多くの民間団体とは大きく異なる特徴がある。政府と経済界、複数のNGOが連携する仕組みを持つ点だ。現在、JPFの活動資金の約8~9割が政府予算である一方、100社を超える賛助企業・団体や、個人からの寄付を含めた予算が加わる。
JPFはこうした資金を、加盟団体に配分する役割を担う。災害・紛争支援のハブとして、国内外で存在感を強めている。
47のNGOが加盟
JPFが設立されたのは2000年。その契機となったのは、前年に起きたコソボ紛争だった。当時、とあるNGOの職員だったJPFの創設者である大西健丞氏(現ピースウィンズ・ジャパン代表、参考記事)は現地で、国連や大手NGOが動く中、日本のNGOが資金力の乏しさからプレゼンスを発揮できない現実に直面した。
ちょうどその頃、日本の外務省はODA(政府開発援助)の活用にあたってNGOとの連携を模索していた。一方で、民間企業も企業の社会的責任として人道支援活動に関心を示していた。大西氏はこれらの動きを結びつけ、官・民・NGOの三者が協働する仕組みの構築を提案。こうして、JPFが誕生した。
設立当初、政府による資金は5億円にとどまっていたが、現在では毎年の助成金は約40億~60億円規模に拡大。これまでに65以上の国・地域で、総額967億円となる事業を展開してきた。
設立当初は政府資金が中心だったが、民間資金の比重も徐々に高まっている。味の素や伊藤忠商事、ANAなど100社を超える企業が支援企業として名を連ねる。能登半島地震のあった2023年度には民間からの寄付は14億円に上り、活動資金総額約74億円の約2割を占めた。

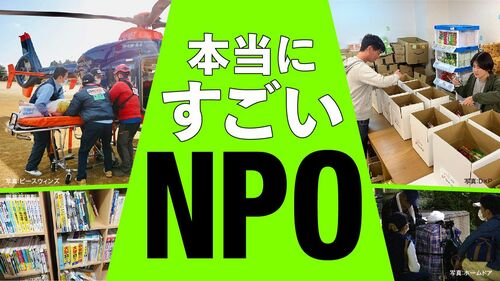
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら