異色の国内最大NGO「生みの親は外務省と経団連」→官と民をつないで加盟NGO47団体へ助成金・寄付金を分配、被災時は現地調査員が緊急対応
一方、安定した事業運営には課題もある。JPFの基盤となる政府資金や寄付金は、大きな災害の有無や政治状況、人々の関心度によって大きく左右されるからだ。
最近ではアメリカのトランプ政権による国連予算の削減や、ODAに対する批判の高まり、さらには日本国内における「自国優先」の風潮が、活動の逆風となっている。こうした声が高まれば、日本でも政府予算が大きく減る可能性もあるほか、企業や個人からの支援も減っていく可能性がある。
しかし多くの場合、支援は1年きりでは終わらない。人道危機は長期化しやすく、巻きこまれた人々が自立するには継続的な支援が必要となる。国内の災害においても、平時から次の災害に備えるための取り組みも必要とされている。災害の大きさや注目度にとらわれず、安定した寄付が必要だが、難しい現状がある。
寄付が安定しなければ、組織運営も不安定になりかねない。JPFでは緊急時にはタフな働き方が求められることもあるが、スタッフの平均年齢は上がりつつあり、若手人材の確保が難しい。
「20代は社会課題に対する意識は高いが、他業界と比べた給与の低さなどを理由に採用が難しい」(上島氏)からだ。近年は少しずつ待遇改善が進んでいるものの、持続可能な働き方の構築が求められている。
求められる制度面からの支援
とりまく環境は厳しいが、やりがいは大きい。上島氏は支援を通じて住民の幸福度が高まるだけでなく、「災害現場でNGOが行ってきた支援の必要性が認められ、災害救助法などに反映される予算につながっている」と語る。NGOは社会に足りていない支援をいちはやく見出し、それを制度として社会に実装する役割も担っているのだ。
「日本では人道支援は官がやるべきだという意識が根強く、海外のように市民による自発的支援が根づきにくい」と上島氏は指摘する。だからこそ、JPFのように官民を巻きこむ組織が果たす役割は大きいだろう。
企業もまた、支援の担い手として重要な役割を果たしている。災害や人道危機への支援は、利益とは異なる形で社会に貢献するものであり、昨今の企業にはこうした取り組みが期待されている。「どのNGOと組んだらよいかわからない」というときには、複数のNGOを抱えるJPFへの寄付が有力な候補となるだろう。
企業によるNPOへの関わりを増やすには、制度面での後押しも欠かせない。例えば東日本大震災や能登半島地震の際には、被災者支援活動を行う団体に対して法人が寄付した場合、全額損金算入が認められてきた。
こうした枠組みが、災害支援に取り組む法人への平時の寄付にも認められるなど、継続的に支援しやすい環境を整えることが求められる。
以下では、ジャパン・プラットフォームの概要や企業との連携などを紹介する。

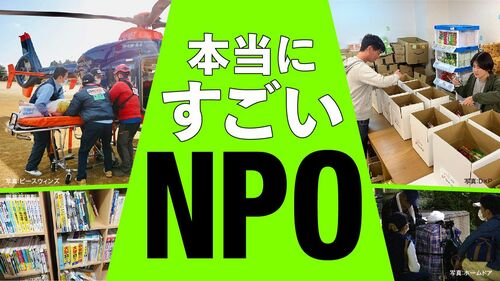
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら