異色の国内最大NGO「生みの親は外務省と経団連」→官と民をつないで加盟NGO47団体へ助成金・寄付金を分配、被災時は現地調査員が緊急対応
JPFはこうした資金を、さまざまなNGOに分配していく。JPFには現在、日本赤十字社やセーブ・ザ・チルドレンなど、47の団体が加盟している。各団体の得意領域を見極めながら、支援事業を委託している。
NGOへの資金配分を行うという立場上、JPFはいちはやく災害や人道支援の現地状況を見極めなければならない。しかし能登半島地震のように、現地からの報道がなかなか出ないこともある。
そのためJPFには、緊急の現地調査を行う調査員がいる。早ければ発災当日、遅くとも3週間以内に現地の状況を精査し、支援事業の立ち上げを検討する。
ときには「メディアなどよりも先に、被災現場に入ることもある」(JPFの上島安裕・共同代表理事)。能登半島地震の際には、スタッフが悪路を数時間かけて乗り越えて現地を視察。まだ報道されていなかった被害の大きさを目の当たりにし、支援事業の立ち上げに至った。
緊急対応を支える審査
事業立ち上げの次に行うのは、JPFに加盟するNGOから申請される支援内容の審査だ。JPF内部だけでなく外部の専門家による審査を経て、事業審査委員会で正式決定される。どの地域に強いか、どのような支援ができるかなど、団体ごとの特性を活かした事業ができあがる。
このスピード感を担保するためには、NGO団体が加盟する「入り口」での審査が重要となる。「加盟する団体がどのような体制かを審査することが、もっとも重要な部分」だと上島氏は語る。加盟団体の審査においては、資金管理体制やハラスメント防止策といった要素も含まれている。
審査を経たNGOが現地に入り、各国の大使館や国際機関などと連携しながら支援を展開する。
「能登や東日本などの国内はもちろん、例えばパレスチナ・ガザ地区でも、井戸からくみ上げた水の供給、疲弊した人々への心理社会的支援など、日本のNGOによる現地の人々の主体性や文化を尊重したきめ細やかな活動が、支援を受けた人々から高く評価されている」と上島代表は語る。
JPFは、国内での災害時に「支援の連携・調整役」としても機能する。東日本大震災時には国内外からのボランティアの受け入れ体制に関して、行政と民間組織、民間組織同士の連携に課題があったが、今ではJPFが各自治体や民間組織、大使館などとの調整機能を果たすようになった。
上島氏は「これまでは海外支援がメインだったが今後は、国内の防災に関する事業なども増えていくだろう」とみている。

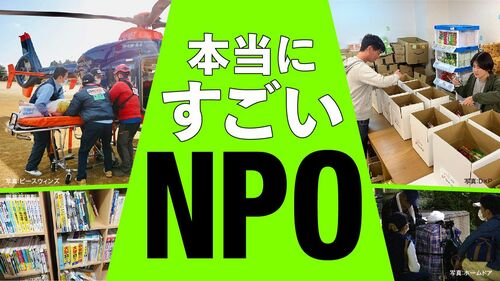
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら