「企業の外側に、ビジネスを生み出す大きなチャンスがあるのだということを実感しました。グローバル企業のマネジメント層は『新しいアイデアを取り入れていかないと、取り残される』と危機感を持って、オープンイノベーションに取り組んでいます。それが企業の成長につながっています。僕の専門分野である宇宙技術の分野にも、応用できるのではないかと考えています」
藤原さんが、この授業から学んだのは、「ゆるく考える」ことの重要性だ。
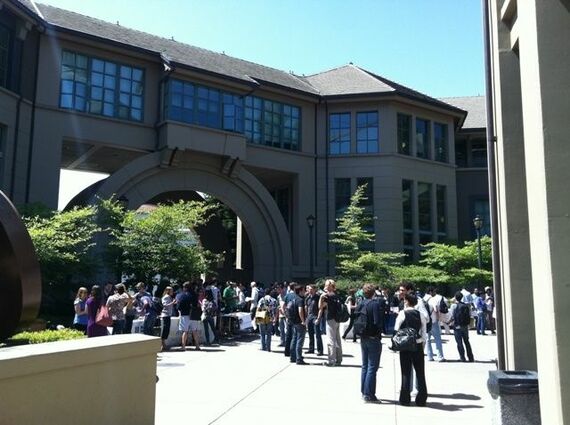
日本企業では、大企業になればなるほど、研究開発・技術開発のプロセスがきっちり整備されていて、社内の論理で、どの技術が製品化されるか決まっていく。
ところが、社内の論理と、社外のニーズは違う。プロセスの中で採用されなかった技術の中に、宝が眠っている場合も往々にしてある。社内の論理やプロセスにこだわるあまりに、ビジネスチャンスを逃している場合もあるのだ。
「シリコンバレーでは、Minimum Viable Product(最低限のスペックがそろったテスト商品)で、まず市場のニーズを測るというのが一般的です。完全に全部作ってしまわないで、最低限のスペックから、ニーズに応じて、改良していくんです。市場に製品を育ててもらうという発想です」
製品を最低限のスペックで市場に出すなんて、高機能・高品質にこだわる日本企業には抵抗感がありそうだが、日本でこうした考え方を浸透させていくことは可能なのだろうか。
その問いに対して、藤原さんは、チェスブロウ教授の言葉を引用して、答えてくれた。
「『技術はそこにあるだけでは、価値はない。製品やサービスなど、世の中に出て、初めて人の役に立つのだ。技術と社会をつなぐ役割をするのが、オープンイノベーションだ』とチェスブロウ教授が言ったのが印象に残っています。イノベーションは、エンジニアだけではなく、社員全員で取り組んでいくべき仕事なのです」
藤原さんが卒業後、どんな道を選択するのか、楽しみだが、「イノベーション」にかかわっていくことだけは、間違いなさそうだ。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら































無料会員登録はこちら
ログインはこちら