
リーダーは誰よりも前に出て、意思決定し、旗を振るものだ──。
これが、長年理想とされてきたリーダー像でした。
しかし本当に、組織を動かすために、リーダーは「動かなければならない」のでしょうか。
薩摩藩の「テゲ流リーダーシップ」とは?
かつて薩摩藩には、「テゲ」という言葉がありました。
「ほどほどに」「適当に」と訳されるこの言葉は、表面的には頼りなく聞こえるかもしれません。しかし実は、組織を強く動かすための、深い知恵が込められているのです。
西郷隆盛も、大村益次郎も──この「テゲ」の精神によって、大きな勢いをつくり出しました。いま、変化の時代を生き抜く私たちにこそ、テゲ流リーダーシップが必要なのかもしれません。
「将たる者は、下の者にテゲにいっておく」と言われていたそうです。
つまり、「テゲ」とは、大きな方針だけを示し、細かなことは現場に任せるリーダースタイルを意味します。リーダーが前面に出すぎず、現場の勢いを信じて見守る──そんな柔らかくも強い統率術です。
幕末の西郷隆盛は、まさにこの「テゲ」に徹していました。
自らは精神的支柱となり、細かな指示や統治には立ち入らなかったのです。
長州出身の児玉源太郎も、台湾総督時代には後藤新平に民政を一任し、自らは前面に出ることなく統治を支えました。しかし、日露戦争が始まると、児玉は薩摩出身の大山巌を総司令官に据え、自らが作戦の実務を指揮しました。もちろん、大山はテゲに徹し、現場介入することはありませんでした。テゲでありながら、状況に応じて「動く」「控える」を自在に使い分けたのです。

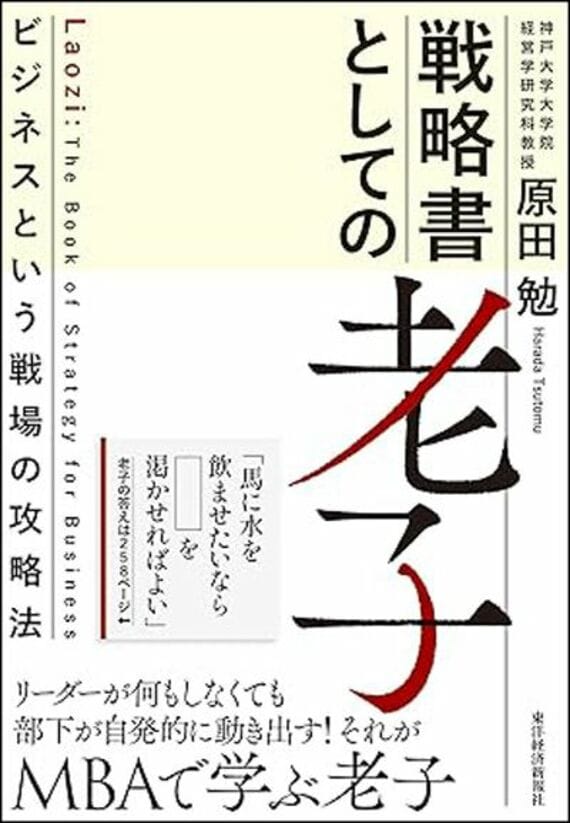



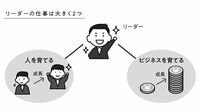




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら