先に述べたように、私たちはこれまで、「リーダーとは旗を掲げ、組織を引っ張るものだ」と信じてきました。誰よりも早く意思決定し、誰よりも責任を取り、誰よりも先に動く──。
けれども、変化の激しい現代では、ひとりのリーダーの判断だけでは間に合いません。指示を待つのではなく、全員が自律的に動ける組織。誰かに依存せず、チーム全体で判断し、行動できる組織。これこそが、これからの時代に求められる組織像だといえるでしょう。
つまり、リーダー自身が「自分がリーダーだ」という意識を手放したとき、はじめて本当のマネジメントが立ち上がるのです。
ここで誤解してはいけないのは、「リーダーがいない=無秩序」ではない、ということです。必要なのは、「誰が指示するか」ではなく、「どう判断し、どう動くか」という共通原理なのです。
この共通原理を示すことこそが、テゲ流リーダーに求められる最も重要な役割です。
戦前の日本陸軍では、共通原理が欠けたため、現場の暴走が続発しました。
ノモンハン事件、インパール作戦、満州事変──。どれも、トップの意志があいまいなまま、現場が独断専行してしまった悲劇でした。
共通原理なき自由は、無秩序に堕します。テゲとは、放任ではありません。自由の背後に、しっかりとした原理を隠し持つことなのです。
「診断」「観察」「処方箋」で勝利を重ねる
テゲ流リーダーにとって、もう一つ大切なことがあります。
それは、「勢い」をつくることです。
西郷隆盛は、大義を掲げ、部下の心を震わせることで勢いを生み出しました。
彼は理念と情熱で組織を動かす天才でした。
一方、大村益次郎は、冷静に情勢を読み、合理的に戦局を設計することで勢いを生み出しました。医学を学んだ彼は、戦場を「診断」し、敵情を「観察」し、作戦という「処方箋」を書くようにして次々と勝利を重ねたのです。
感情で火をつける西郷。
流れを読む大村。
このふたつのリーダーシップは、どちらか一方だけでは組織を持続させることはできませんでした。




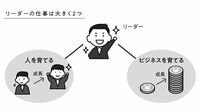




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら