
「貿易と関税に関する一般協定」(GATT)は1947年に誕生した。国際連合、IMF(国際通貨基金)、ドル基軸通貨体制など戦後世界を決定づける国際制度は、おおかた第2次世界大戦後すぐに生まれている。
世界を巻き込んだ大戦において、アメリカ合衆国は直接の戦禍を受けなかったことから世界最強の国となり、そのアメリカの音頭の下にできたのが戦後体制である。
アメリカは、イギリスに代わって世界最強の経済大国になり、世界を1つの貿易圏として創造したのだが、そのための規則を定めたのが、この貿易と関税に関する一般協定であった。
リカードウの「比較生産費説」
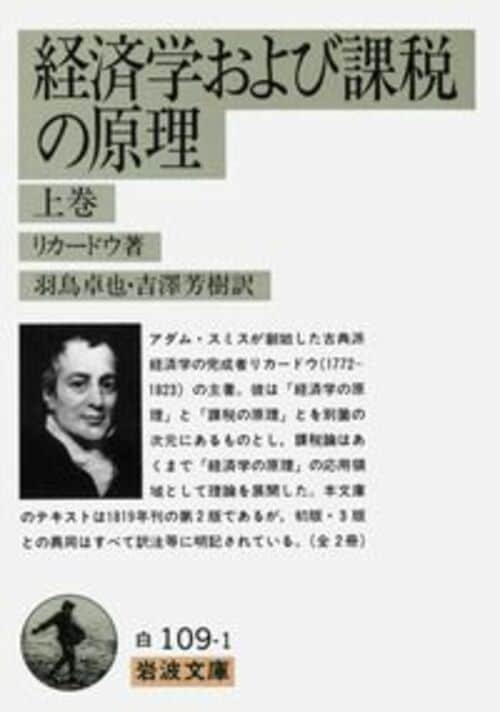
18世紀半ばの産業革命によって世界経済の覇権を掌握したイギリスは、その強い生産力によって世界に自由貿易を押しつけていく。その際、その説得に使われたのが、GATTの協定でも使われたリカードウの「比較生産費説」という理論であった。
要するにお互いが得意なものに特化すればどの国も発展するので、関税なしの自由貿易こそ最良の制度だという議論である。
この議論の根底には、その神話として、デヴィッド・リカードウ(1772~1823年)の『経済学および課税の原理』(1817年)の7章「外国貿易について」で展開されるイギリスとポルトガルの自由貿易の話がある。彼はそこでこう述べている。



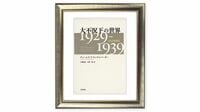

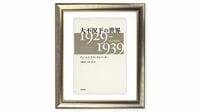



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら