
京都企業の村田製作所に対し、電子部品における「東の横綱」が、東京に本社を構えるTDKだ。2025年3月期の売上高は2兆2048億円。業界で最大級の事業規模を誇る。

受動部品やセンサーなど多種多様な製品群を擁する中、小型のリチウムイオン2次電池を中核に据える。主にスマートフォンのバッテリーに用いられ、世界シェアは5〜6割程度。これを含む「エナジー応用」セグメントの部門売上高は1兆1000億円を超え、営業利益の大半を稼ぎ出す。
まさに大黒柱だが、事業の主体はTDKの本体ではない。05年に買収した中国の子会社、アンプレックステクノロジー(ATL)が主導権を握る。その取得額は約100億円。2次電池部門の最高責任者、指田史雄執行役員は「当初はドラフト4〜5位ぐらいの期待感だった」と振り返る。
屋台骨は時代ごとに変遷
いかに大化けを果たしたのか。その経緯をたどるには、TDKの歴史をひもとく必要がある。同社は1935年、フェライト(磁性材料)の工業化を目的に設立。ラジオや無線向け部品に始まり、時代ごとに看板製品を入れ替えて発展してきた。「カメレオン経営」と称されるゆえんだ。


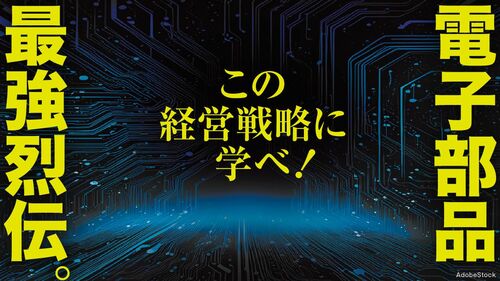































無料会員登録はこちら
ログインはこちら