
東京証券取引所で経営陣が鐘を鳴らしてから10カ月。華々しく市場に迎えられたベンチャーはあっという間に散ることになった。
2024年10月に東証グロースに上場し、「大型ベンチャー」ともてはやされた人工知能(AI)開発のオルツが7月30日、東京地裁に民事再生法の適用を申請した。同日、東証はオルツを8月31日付で上場廃止にすることを決定した。
極めて単純なスキーム
発端は4月初旬、オルツが証券取引等監査委員会の調査を受け、全社収益の9割を稼ぐ議事録作成サービス「AI GIJIROKU」をめぐり、売り上げの過大計上疑惑が浮上したことだ。同社はこれを受けて第三者委員会を立ち上げ、調査を開始した。
7月29日にオルツが開示した第三者委員会調査報告書の内容は衝撃的だった。当初の疑惑通り、AI GIJIROKUにおいて行われていた不正会計のやり口が、非常に単純だったのだ。

AI GIJIROKUは年間利用料を払って使えるライセンス(アカウント)を自社サイトでの直販のほか、代理店経由での販売を行っている。その際、「スーパーパートナー(SP)」と銘打った販売パートナーを経由して販売しており、SPについては利用アカウントをバルクで販売した時点で売り上げを計上していた。
ところが報告書によると、オルツからSPに対するアカウント販売の発注行為は確認できるものの、実際にはSPにライセンスが発行された形跡は確認できず、取引の実態は認められなかった。一方で、広告費、あるいは研究開発費の名目で広告代理店などに支払われた資金がSPに渡されていた。
報告書は、「このような資金を循環させる取引実態をもってすれば、本件SPスキームによる資金循環はいわゆる『循環取引』に他ならない」と結論づけている。

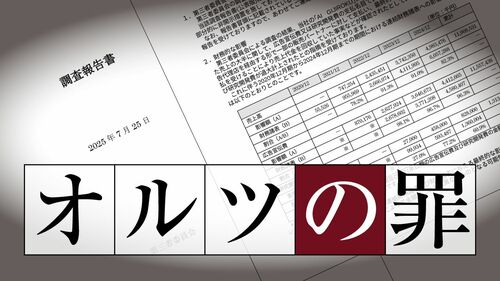


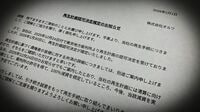






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら