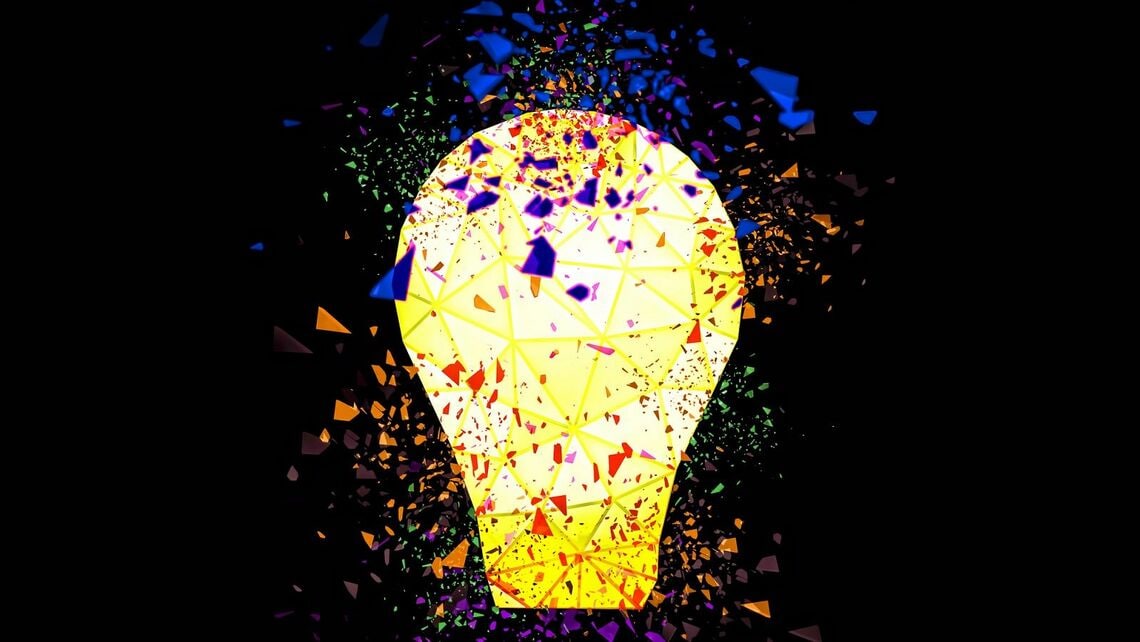
日本企業が栄華を誇っていたのはもはや過去の話。バブル崩壊前の1989年まで、時価総額ランキングトップ5を独占していた日本企業はランク外に落ち、今の20代が物心ついたときには、「そんな時代があったのか」という感覚なのかもしれない。

そうした中、日本政府は2022年11月に「スタートアップ育成5か年計画」を発表し、スタートアップに対する年間投資額を2027年度に10兆円規模へ増やす目標を掲げるほか、大企業も業種業界を問わず、新規事業創出を行っている。
こうした取り組みは一定の成果に結び付いていると思われるものの、まだまだ限定的な印象がある。著者が経営するスタートアップスタジオ・quantum(クオンタム)は、2010年代初頭から新規事業開発やスタートアップ創出に関わる業界の動向に注目してきたが、その頃からうまくいっている事例として挙げられるベンチャー企業やスタートアップの顔ぶれも大きく変わっていない。
教科書に沿った事業開発の限界
これだけ政府、経済界、大学や研究機関が懸命に力を注いでいながら、なぜ破壊的なイノベーションの創出に苦戦するのだろうか。私は、その理由の1つが「科学的に段取り化されすぎたイノベーション創出のアプローチ」であると考えている。
過去に何度も新規事業やスタートアップを立ち上げてきた「シリアルアントレプレナー」のような存在はごく稀で、大企業にせよ、起業家候補にせよ、初めて事業開発に取り組むことになるケースが大半だ。そうなると、人は「手すり」を求めるものである。暗闇の中、どこに向かって歩いていけばいいのか? 不安な中、頼れる手すりがあるとそれをつたっていきたいと思うだろう。
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら