株式市場を救った半導体大手エヌビディアの規格外決算。それでも消えない「AIバブル懸念」
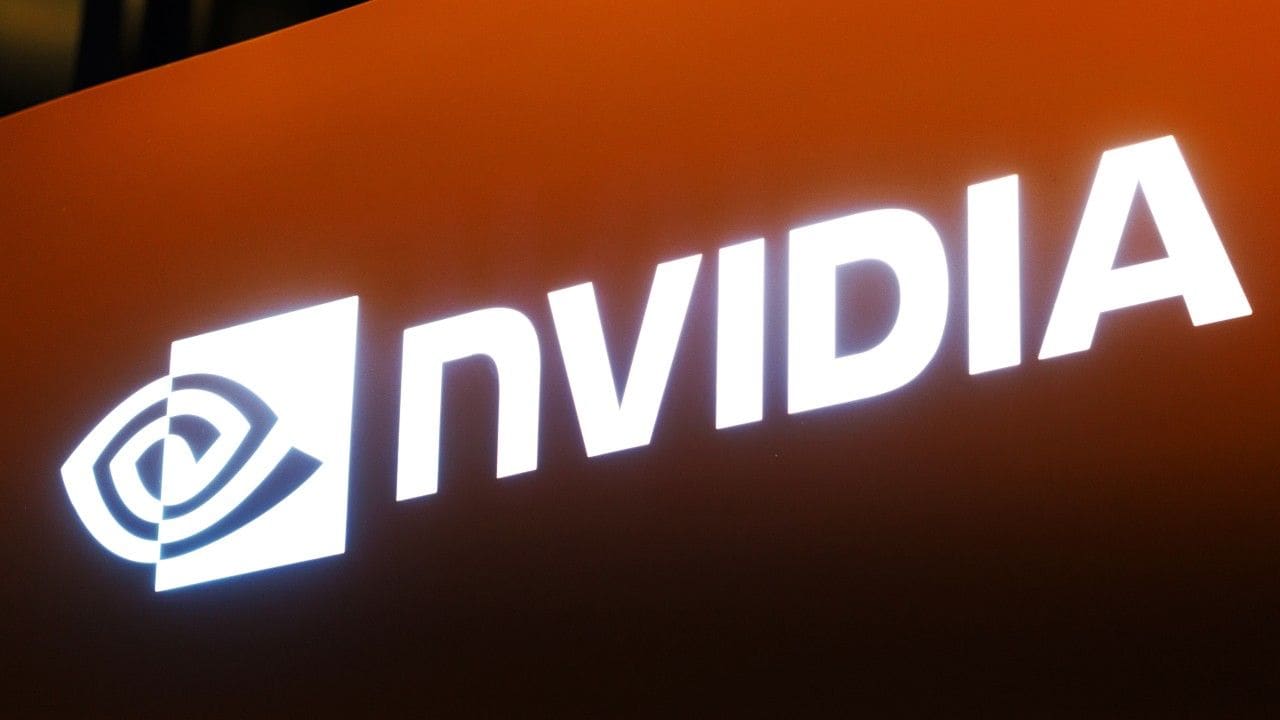
エヌビディアが現地時間11月19日に発表した2026年1月期の第3四半期(8~10月)決算は、まさに規格外だった。
売上高は約570億ドル(約9兆円、前年同期比62%増)、データセンター部門の売上高は全体の9割を占める水準に達した。昨年から懸念されていた粗利益率も73.4%と計画どおりの改善を見せ、EPS(1株当たり利益)も市場予想を上回った。第4四半期のガイダンス(業績見通し)も予想を上回る強気なものであった。
決算発表直前の株式市場では、「AIブームは実体を伴わないバブルではないか」という懸念が強まっていた。エヌビディアの株価は11月に入ってから調整し、同社が主な構成銘柄となっているナスダック総合指数も伸び悩んだ。
こうした中で市場関係者を安堵させたのが、「AI向けGPU(画像処理半導体)需要は依然として旺盛で、26年までの受注残も巨額である」というエヌビディア経営陣からのメッセージだ。少なくとも足元の数字だけを見れば、「AI関連の相場テーマはもう終わり」という弱気シナリオは後退したと言ってよい。
市場の反応も即座であった。エヌビディア株は決算発表後の時間外取引で急騰し、ほかの半導体、クラウド、生成AI関連株にも買いが波及した。指数ベースでもナスダックやS&P500指数の先物が上昇に転じ、「エヌビディア決算が、調整相場入りの瀬戸際で市場を救った」という評価が多い。
ライバル「AMD」の攻勢
もちろん、エヌビディアも独走を許されているわけではない。
競合のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)は、MI300シリーズなどデータセンター向けAIアクセラレーター(AIの学習や推論の高速化を支えるハードウェア)で攻勢を強めている。
AI向けGPUとサーバー向けCPU(中央演算処理装置)を軸にデータセンター部門の売上高が急拡大しており、オープンAIやオラクルなどとの大型提携を通じて、「“エヌビディア依存”を避けたい顧客企業にとっての第2の選択肢」として存在感を増している。AMDの株価は25年の年初から2倍近くまで上昇しており、市場も同社のAI向けGPU領域での本格攻勢に対して期待感を持っていることがわかる。
ただ、それでもなお現時点でエヌビディアの優位は明確である。
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら