高市早苗政権「労働時間規制の緩和」への違和感/上限規制は企業活動を大きく制約していない/労働者の多くもさらなる長時間労働を望んでいない

政権発足直後、高市早苗首相が「心身の健康維持と従業者の選択を前提とした労働時間規制の緩和の検討」を指示し、大きな議論を呼んでいる。
ワーク・ライフ・バランスの改善を目指す従来の働き方改革に逆行するとの指摘も目立つ。ここではデータに基づき、「労働時間規制で企業は本当に困っているのか」、そして「労働時間の増加を労働者は望んでいるのか」という2つの観点から考えてみる。
残業時間の上限規制
労働時間規制の中心は、2019年から順次導入された残業時間の上限規制である。36協定(時間外・休日労働に関する協定)を締結する企業の場合、年360時間、月45時間が罰則付きの上限だ。
特別な事情があり労使が合意する場合(特別条項)でも年720時間、月100時間(2〜6カ月平均80時間〈いずれも休日労働含む〉)、月45時間超過は年間6カ月までと定められ、従来の実質的に上限がない状況は解消された。

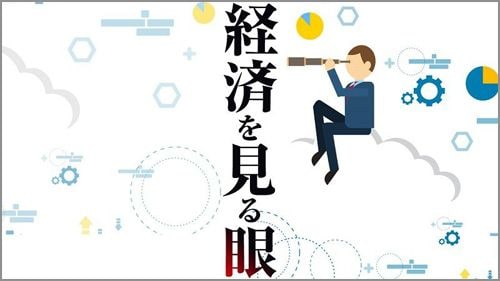































無料会員登録はこちら
ログインはこちら