
11月7日に高市早苗首相が国会で行った答弁が議論を巻き起こし、日中間の外交問題にまで発展した。高市首相は日本の「存立危機事態」に関する答弁で、「台湾に対し武力攻撃が発生する。海上封鎖を解くために米軍が来援し、それを防ぐために武力行使が行われる」という想定に言及し、「戦艦を使って武力の行使を伴うものであれば、どう考えても『存立危機事態』になりうるケースだ」と述べた。
この答弁に中国が激しく反発する中、日本国内でも議論が続いている。答弁について日本政府は「従来の政府の立場と変わらない」とし、高市首相も答弁撤回を否定した上で「今後は特定のケースを想定したことを国会で明言することは慎む」と発言を修正した。
これに対し、一部野党や識者・ジャーナリストの中からは、「答弁は従来の政府の立場を逸脱したもの」「台湾は中国の一部であるから高市首相の答弁は間違い」などの声が上がる。台湾を自国の一部と主張する中国も「内政干渉だ」と反発し、日本産水産品の禁輸や自国民に日本への渡航の自粛を求めるなど対抗手段に出た。一方で、答弁を撤回して事態の鎮静化を図れとの主張も日本国内の一部から出ている。
ただし、現状の台湾を変更したい中国が、武力行使の可能性を否定しないまま、台湾への武力侵攻を思いとどまり、「平和統一政策」という実力行使を控えた方針を、表向き今なお採り続けるのは、これまで積み重ねられてきた日中米台を中心とした東アジアの国際関係がつくり出した構図に基づく。それゆえ、今回の高市首相の答弁の妥当性や撤回するか否かも含めて、議論に際しては歴史的経緯や構造を踏まえることが必要である。
日中共同声明の懸案は台湾問題
台湾に対する日本政府の立場については、九州大学の前原志保准教授による解説論考「新聞ですら間違える『台湾問題』への日本の立場」(11月18日配信)に詳しく書かれている。1972年の日中共同声明でも、台湾を中国の一部とする中華人民共和国政府の主張に日本政府が完全には同意していないことに関しては、同論考を参照してもらいたい。
それでは、なぜ日本政府は中国側の主張に完全には同意せず、前原氏が指摘するように「『議論の余地は残す』という外交の妙味を持たせている」のだろうか。この日本政府の絶妙な立場の背景には、安全保障上の理由も存在している。
72年に日中共同声明を出す際に日中間で最大の懸案事項となったのは、台湾をめぐる立場の違いだった。中国側は台湾が中国の一部であることを承認するよう日本に求めた。一方で、日本はサンフランシスコ平和条約で台湾の帰属先を明言せずに放棄したことなどから台湾の帰属先や主権について言う立場にはないという姿勢だった。



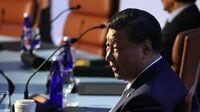





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら