
「顧客のところに300回行け」は普及したが…
「顧客のところに300回行け」は、新規事業開発における最も根本的な考え方であり、前作『新規事業の実践論』を代表する教えです。
既存事業であったら重要とされる9つの単語「確認」「事例」「調査」「会議」「資料」「社内」「上司」「先輩」「競合」をいっさい排除する。それによって紡ぎ出された可処分時間と隙間時間をすべて、顧客のところに行くことに使う。仮説と顧客のサイクルをただひたすら回すことにのみ集中する。
すると、その行動が300回転を迎えるころに、それまでに積み上げたすべての情報の点と点が1本の線でつながり、新規事業案が出現し、立ち上がっていく。
それほどまでに「顧客」に集中することでしか新規事業は立ち上がらないことを、前作では解説しました。
改めて「顧客のところに300回行く」ことが最も重要な考え方であると示したうえで、本記事では「その深い本質」を解説します。

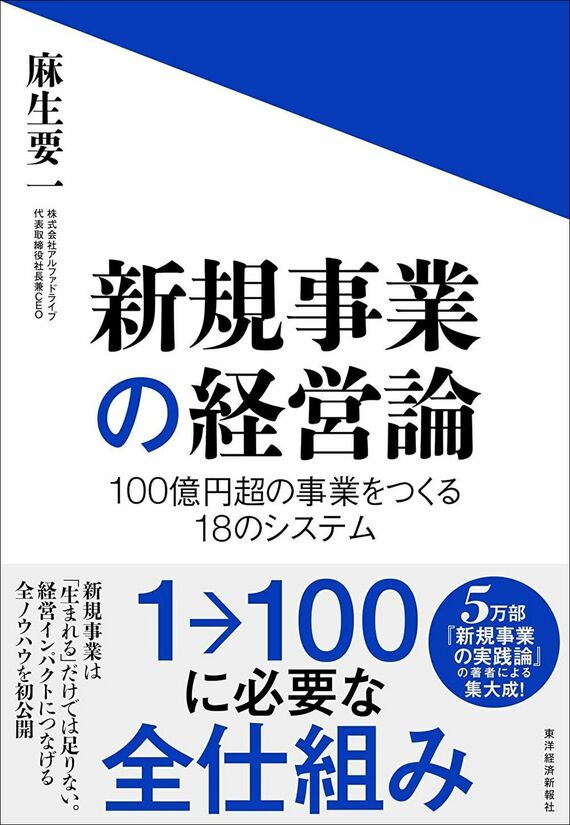
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら