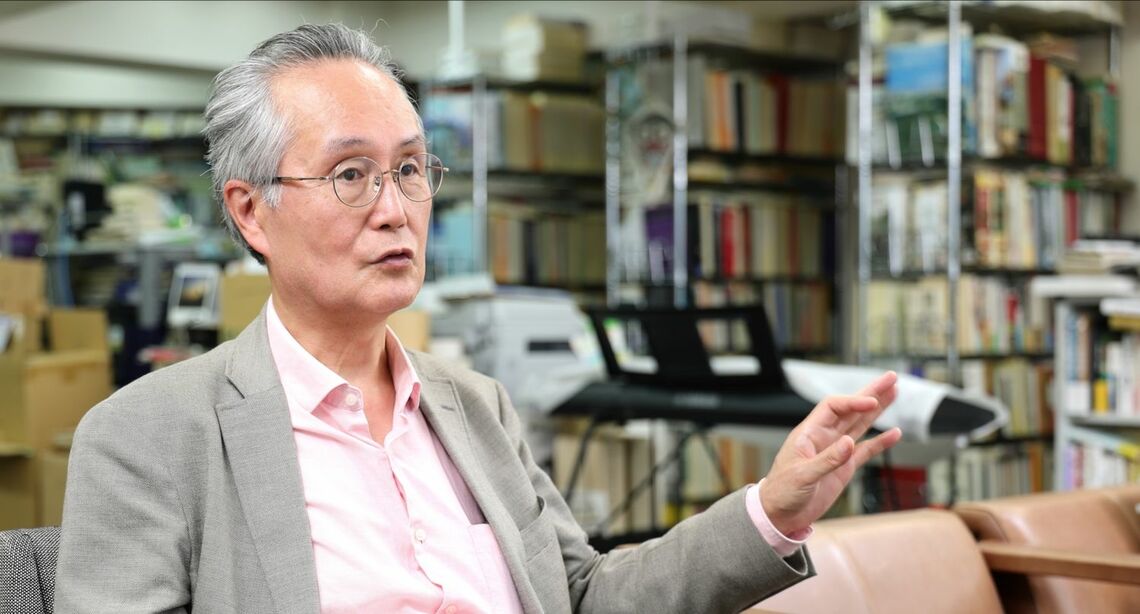 小野塚 知二(おのづか・ともじ)/東京大学特任教授、東京大学エグゼクティブ・マネジメント・プログラム(東大EMP)コチェア。1957年生まれ。1987年東京大学大学院経済学研究科第2種博士課程単位取得満期退学。2001年東京大学大学院経済学研究科教授。2022年から現職。主な著書に『経済史』、編著に『第一次世界大戦開戦原因の再検討』など(写真:尾形文繁)
小野塚 知二(おのづか・ともじ)/東京大学特任教授、東京大学エグゼクティブ・マネジメント・プログラム(東大EMP)コチェア。1957年生まれ。1987年東京大学大学院経済学研究科第2種博士課程単位取得満期退学。2001年東京大学大学院経済学研究科教授。2022年から現職。主な著書に『経済史』、編著に『第一次世界大戦開戦原因の再検討』など(写真:尾形文繁)
――トランプ大統領は「アメリカを再び偉大な国にする」と言いますが、いったいどの時代に戻りたいのでしょうか。
おそらくトランプ政権に歴史の参照軸はない。通商政策とは一貫して大人の慎重で冷静な技だったが、それを世界最大の国の大統領とその取り巻きが子どものおもちゃに変えてしまった。
貿易体制の歴史は、250年のタイムスパンで考えなければならない。18世紀半ばに始まった産業革命のさなかで、自国の産業を保護するための保護関税は当たり前、関税率は2国間の協定や条約で決めるのではなく、その国が勝手に決めていた。いわゆる重商主義の時代だ。
1776年に初版が刊行された『諸国民の富』で、アダム・スミスは重商主義政策を批判した。同じ年にアメリカの独立宣言が採択され、アメリカ合衆国という特殊な国ができた。
保護主義を貫いてきた唯一の例外国
――アメリカはどう特殊なのですか。
基本的に国内でモノがこと足りてきた数少ない国で、保護主義を国是に成り立ってきたという特殊性がある。決して自由貿易の秩序を重んじてきたわけではない。トランプ大統領がその歴史をどこまで知っているのかはわからないが、高関税を持ち出すのはそれを体現している。
自由貿易の考え方は19世紀になって初めて登場し、1860年代にはヨーロッパとアジア、中南米で自由貿易の秩序ができあがった。唯一の例外がアメリカだった。
――自由貿易はどのように広がったのですか。
経路は2つある。1つが、安い穀物を輸入するために関税を引き下げるものだ。産業革命が最初に進行したイギリスでは、商工業人口が増えると耕作に向かない土地でも食料生産しなければならず、上がった地代を反映して食料価格が上がった。すると資本家は賃金を引き上げなければならず、利潤が損なわれる。利潤を獲得できなければ資本主義は死滅すると危惧された。
そこで、経済学者の論争が起きた。マルサスは、世界中で人口が増え、あらゆる土地を耕しても食料が足りずに資本主義が成り立たなくなるとして人口抑制を唱えた。
それに対してリカードは、いずれ食料不足で経済成長できない状態になるとしても、当面は世界全体で見れば食料は足りているのだから、食料が余っているドイツやロシアから輸入すればいいと主張した。
その主張通りに進んだわけではないが、イギリスは1846年に穀物法を廃止して穀物輸入を自由化した。これは相手国に対して関税引き下げを求めるものではなく、イギリスにとって安い穀物が手に入るメリットがあればいいという一方的自由貿易だった。

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら