大将の君は、督の君が思いあまって、それとなく口にしたことを、「いったい何があったのだろう、もう少し意識がしっかりしている時だったら、あんなふうに言い出したことなのだから、もっとよく事情はわかったかもしれないのに……。どうにもならない臨終の間際で、じつに折悪く、なんだか気掛かりなまま、悲しいことになってしまった……」と、面影を忘れることができず、兄弟の君たちよりも無性に悲しく思っている。「姫宮がああして出家なさったことも、そうひどいご病気というわけでもなかったのに、よくぞきっぱりとご決心なさったものだ、それにしても父院(光君)がお許しになっていいことなのか……、二条の上(紫の上)があれほどに危篤状態で、泣く泣く出家をお願いなさったと聞いたけれど、父院はとんでもないことだとお思いで、結局こうしてお引き留めになったというのに……」などと、あれこれ思案をめぐらせて、「やはり前々から、督の君には姫宮を思う気持ちがあって、それがときどきこらえきれなかったのだろう。うわべはひどく冷静で、ほかのだれよりも思いやりがあり、穏やかで、この人はいったい心の内ではどう思っているのだろうと、はたの人も気詰まりなくらいだったけれど、少し弱いところがあって、やさしすぎたのがいけなかったのだろう。どんなにつらい思いをしても、道ならぬ恋に心を乱して、こんなふうに命に代えていいはずがない。相手のためにも気の毒だし、それに自分の身まで滅ぼしていいものか。そうなるべき前世からの因縁とはいうが、まったく軽々しい、つまらないことではないか」などと、ひとり胸の内であれこれ思っているけれど、妻(雲居雁(くもいのかり))にもそれを漏らしたりはしない。また適当な機会もなく、光君にも話せないままでいる。とはいえ、「こんなことを督の君がほのめかしていました」と光君に話してみて、顔色を見てみたくもあるのだった。
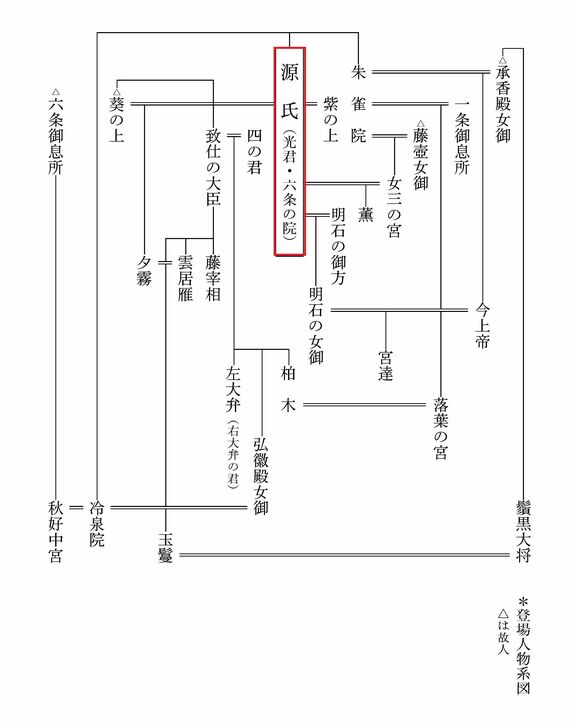
涙の涸れる時なく悲嘆にくれて
督の君の父大臣、母北の方は、涙の涸(か)れる時なく悲嘆にくれて、はかなく過ぎていく日々を数えることもなく、法事の法服、装束、そのほかあれこれの支度も、弟の君たちや姉妹たちがそれぞれに調えている。お経や仏像の飾りなどの指図も、督の君の弟である右大弁の君にさせるのだった。七日目ごとの誦経(ずきょう)についても、ほかの人が注意を促すと、「私の耳に入れるな。こんなにもつらいと親の私が悲しんでいては、かえって成仏の妨げとなってしまう」と、死人のように虚(うつ)けている。
次の話を読む:10月27日14時配信予定
*小見出しなどはWeb掲載のために加えたものです
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら































無料会員登録はこちら
ログインはこちら