「数値化」では世界の本質を理解できない理由 土着人類学で考える社会との折り合いの付け方
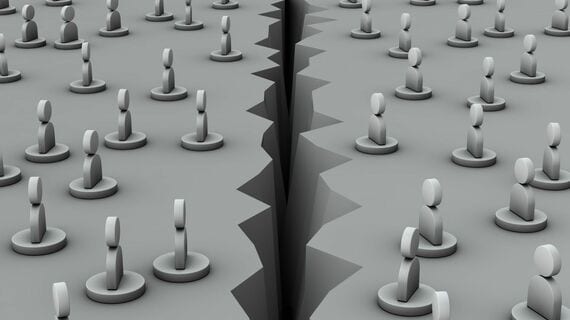
奈良県東吉野村で「人文系私設図書館ルチャ・リブロ」を運営する『手づくりのアジール 「土着の知」が生まれるところ』著者・青木真兵氏が、「土着人類学」の視点から同書を読み解く。
数値化による理解の限界
ぼくが勝手に提唱する「土着人類学」は学問ではありません。言うなれば思想です(おおげさですけれど)。
いわゆる学問は主体と客体、つまり「考える自分」と「考えられている対象」を区別します。特に近代という時代は主体と客体を区別することで、元々は神話や物語によって語られイメージされてきた世界を客観的に把握し、コントロールしようとしてきました。この延長線上にあるのが数字による測定です。世界を数字によって表現することで、ぼくたちはより客観的に理解できるような気になっています。
しかし本来、何にせよ世界を完全に把握することなど不可能です。ではぼくたちは世界を数字で示したとき、何を理解したような気になっているのでしょうか。
ぼくたちが数字によって理解したつもりになっているのは、世界の「量的な側面」です。数値によって表わすことのできる世界は世界それ自体ではなく、「量的な側面」でしかありません。特に近代は「量的な側面」が重視される時代であり、前近代の世界を価値付けていた「質的な側面」が没落していきました。




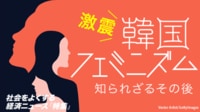




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら