「数値化」では世界の本質を理解できない理由 土着人類学で考える社会との折り合いの付け方
そして土着人類学では、手づくりの原理と商品の原理を行ったり来たりしながら生活を組み立てていくことを試みます。そのためにはまず自分の中にある社会の外部、つまり「自然」を手がかりに「生きた世界」を取り戻す。まずはこれが土着人類学の目指すところです。
繰り返しになりますが、そもそも人類は2つの原理を有して生きていました。しかし近代以降、1つの原理への統一が進んでしまった。それにより人類は国民になり、消費者になっていきました。その結果、量的な部分によって客観的に把握しないと世界を理解できない気になってしまった。
矛盾する状況こそ健全
しかし本来はそうではなく、世界は質的な部分と量的な部分、生き物の部分と死者の部分など、2つの部分が支え合って構成されていたのです。佐伯さんは哲学者の西田幾多郎の思想を紹介しつつ、世界の構造について述べています。
この時、われわれ意志を持った個人(あるいは集団)は、主体として世界へ働きかけることで、社会制度や世界の枠組みや法制度や生産技術といった環境を変えることができる。だが、主体はまた環境から独立しているわけではなく、常に環境によって動かされ、また行動も変化する。こうして、主体が環境を作り、また同時に環境が主体を作るという対立的な相互作用の中で、歴史的世界は、決して立ち止まることなく、時々刻々と変化し続けている。その意味で、それは矛盾的自己同一においてたえず自己自身を形成してゆく世界なのである。(『近代の虚妄:現代文明論序説』427頁)
つまり世界は矛盾するもの、相対する2つのものによって成り立っているのです。
矛盾するものを退けず、無理にどちらか一方に単純化しないこと。むしろ1つに決められない状況の方が、世界を健全に理解することができています。
そして2つの矛盾した状況にあるときこそ、実は豊かな世界に触れている瞬間だといえます。土着人類学によってこのような世界認識を生活の中に取り戻すこと。まずはそれがぼくたちの喫緊の課題だと思っています。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

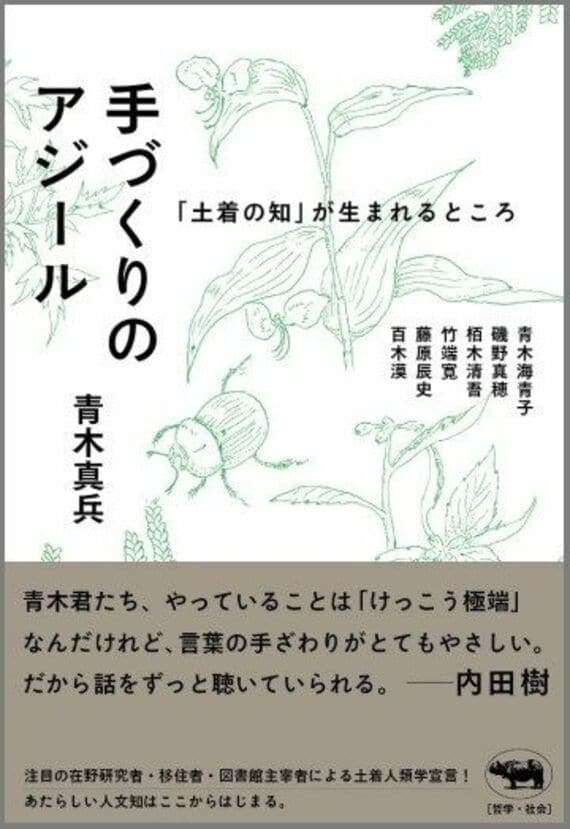


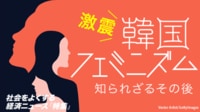




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら