まず、創り手の「熱狂」ありきで、それを独特の感覚を通じてプロダクトに保存する。こうして完成したプロダクトは、これまでのビジネスとは真逆の特徴を備えます。すなわち、プロダクトアウト、つまり、メーカー本位のものづくりに回帰するという特徴です。
これまで語られてきたプロダクトアウトは、コストや投資の論理、社内政治、あるいは技術的限界や技術的優位性をユーザーに押しつけるような意味あいがありました。
しかし、BAMにおけるプロダクトアウトは違います。メーカーが自身の熱狂や原体験を出発点に、世界を前進させるため、卓越したものづくりをする気概を持って生み出します。
未来のユーザーファーストという視点
そもそもアーティストは、鑑賞者のニーズに合わせて作品を創ることはしません。アーティストが熱狂した原体験を鑑賞者にも追体験してもらおうとするため、創り手が常に受け手をリードする関係になります。
これをプロダクトに当てはめれば、メーカーは決してユーザーファーストではなく、常にユーザーをリードしなければなりません。現在のユーザーが望むものを単に提供するのではなく、ユーザーがまだ気づいていない未来の可能性を先取りして具現化することが求められるのです。
言うなれば、現在のユーザーファーストではなく、未来のユーザーファーストなのです。アーティストが作品に向かう時、自分が鑑賞したい作品が世の中にないからこそ創り出しています。創り手であると同時に、それを求める未来の受け手でもあるのです。自分自身こそ未来の鑑賞者という見方ができるのです。
アートとビジネスは、「熱狂を起点とした価値創造」という点で本質的に共通しています。
BAMは、創り手の内なる衝動という「熱狂」を起点とし、「感覚」を通じて「プロダクト」へと昇華され、ユーザーの「感覚」と「熱狂」を喚起していくのです。
創り手の「どうしてもこれを形にしたい」という「熱狂」ありきで、初めてプロダクトの本質的な価値は生まれるのです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

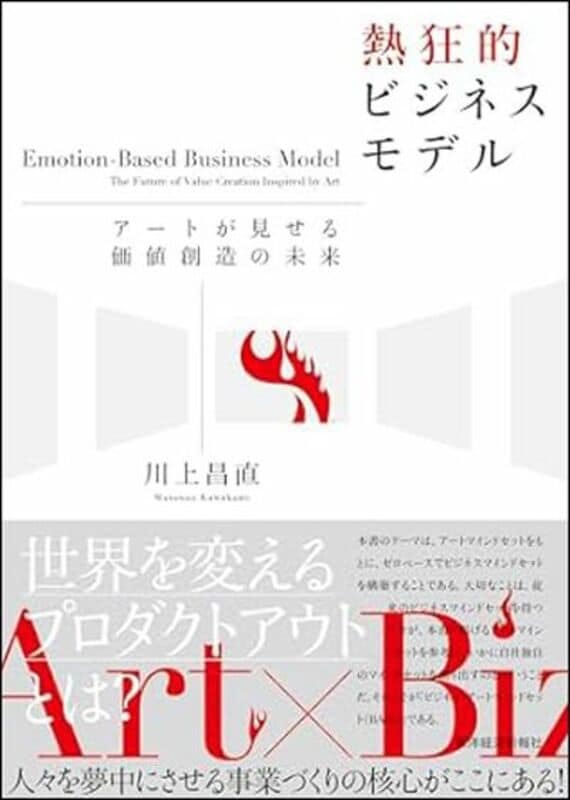































無料会員登録はこちら
ログインはこちら