
仕事にハマらせるための最初のわな
──危険な物語化の例として、就職活動の面接を挙げています。応募者はしばしば、自分の人生を物語化することを強要される、と。
就活は多くの人が困っているテーマだ。特に人文系の大学院で修士を出て就職した友人を見ていて、思うところがあった。働き始めると、仕事にすごくハマっていく。そうなると、忙しくて哲学を趣味で続けるのも難しくなる。
仕事にハマらせるための最初のわなが、就活で物語を語らせることなんじゃないか。面接官の心に響くような筋書きで自己を語っているうちに、そんな気になってしまう。それがすごく嫌で、自分の人生を無理に物語の枠組みに押し込めることに抵抗があった。
──本書は、物語、ゲーム、パズル、ギャンブル、おもちゃ遊びの5つを「遊び」として捉え、その特徴やそれぞれの遊びにおける主体のあり方を考察していきます。5つのカテゴリーは、どのように決まったのですか。
最初に、「物語」と対比するものとして「おもちゃ遊び」が見つかった。そのあと、『プレイ・マターズ』を著したゲーム研究者、ミゲル・シカールの研究を参考にして、「ゲーム」が第3の軸として浮かび上がってきた。さらに自分の周りの友人を思い浮かべる中で、「ギャンブル」や「パズル」というくくりが見えてきた。

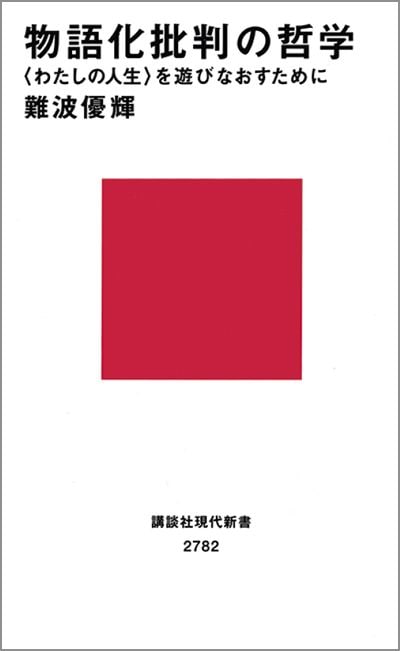



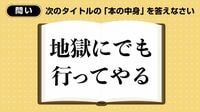



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら