
多くの経営者がM&Aなどの提案を頭から否定する
──今回、コングロマリット経営に関する本を書いた経緯は?
2019年に出版した書籍でも「選択と集中」がもたらす問題については触れた。だが、21世紀に入って四半世紀が経とうとしているのに、いまだに多くの経営者が「本業以外はやらない」「シナジーがない事業はやらない」と主張し、M&Aなどの提案を頭から否定する。これでは膨大な機会費用を生み出しているのと同じだ。
特に財務系の社長や、コーポレートガバナンスを言い訳にする社長にその傾向が強い。今の日本企業は、まるでパリ・コレクションに出られない「やせすぎのモデル」のようだ。もっとぜい肉をつけ、体格を良くしなければならない。
──日本では長らく「選択と集中」という言葉が金科玉条のように扱われてきましたが、それが誤りだとの主張ですね。
そのとおりだ。「選択と集中」を広めたのは、米ゼネラル・エレクトリックで1981年から20年にわたりCEOを務めた「伝説の経営者」、ジャック・ウェルチだとされるが、彼自身は「フォーカス」と言ったにすぎない。
真意は「リソースを集中投下して、どんどん新しいことをやろう」だったはず。それが日本では「新しいことをやるのはダメだ」と正反対の意味で使われている。

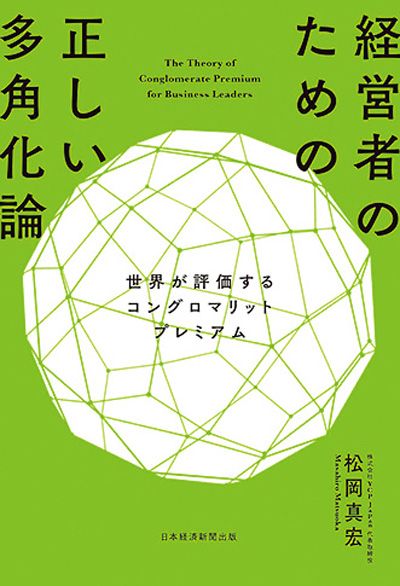

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら