
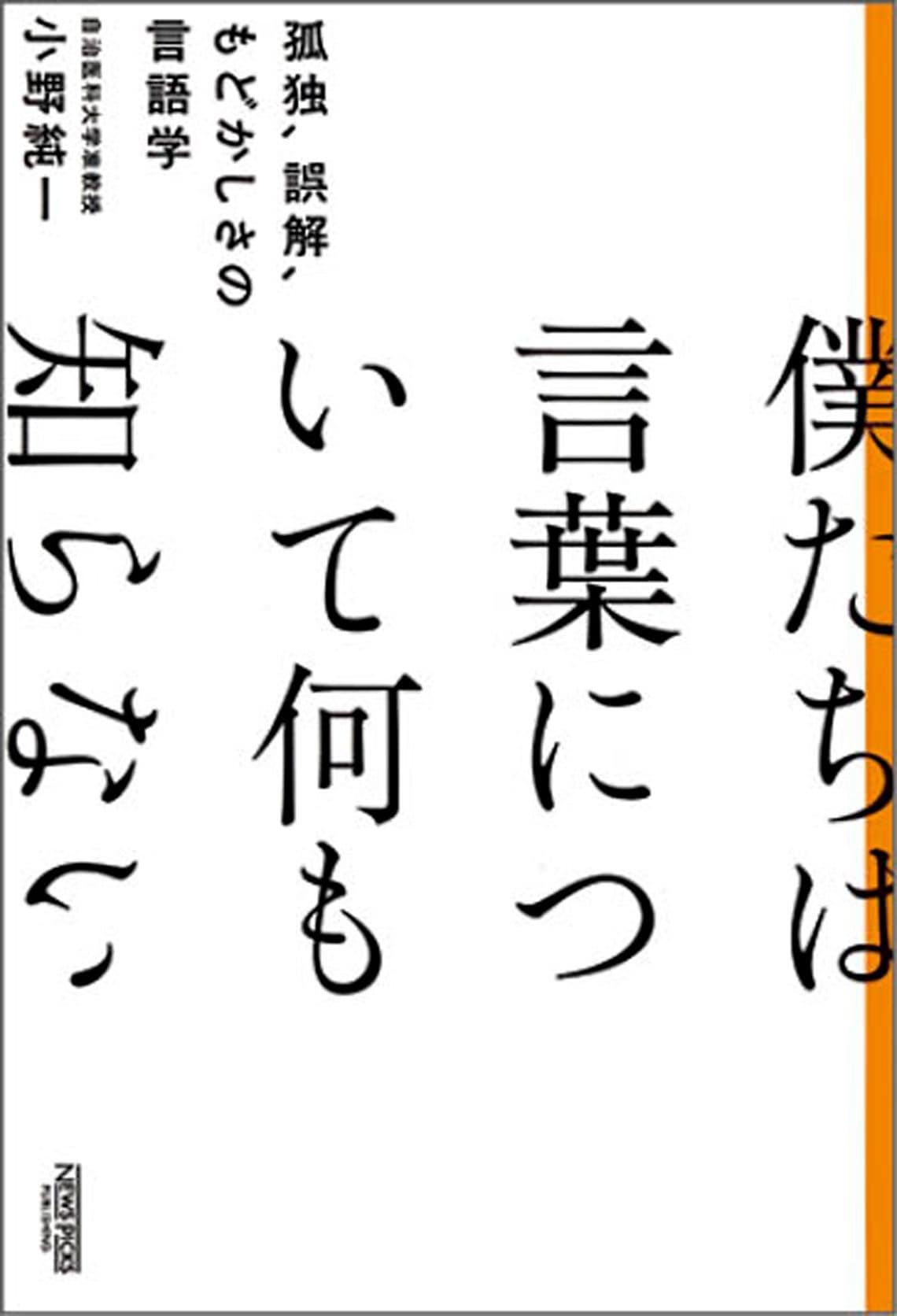
──「誤解させたなら謝ります」にモヤモヤする理由、言語行為としての京都「いけず文化」など、身近な例が取り上げられています。
丁寧なようで相手をいら立たせる言葉、「ぶぶ漬け」のように特定の場や状況が裏の意味を生む現象、あるいは真意がうまく伝わらず抱く後悔。どれも日常生活の延長線上にある言語行為だが、そこには言葉の本質が隠れている。
言語哲学の世界では言葉を、人の心や行動に作用する「呪術」として分析してきた。──と言うと難しそうに思えるかもしれないが、「誤解〜」や「ぶぶ漬け」もその哲学的な考察の対象になりうる。
言葉を使わずに生きるのは難しく、私たちは情報を伝えるために、また言葉を介した心の交流を求めて、毎日多くの言葉を発している。しかし、物心ついて以来言葉とともに生きてきたのになぜいまだにうまく伝えられないのか、よいコミュニケーションとは何か? その普遍性を考えることが読み手にとって新たな視点の獲得、哲学の目的である善き生(幸せ)の実現につながればと、この本を書いた。
今、多くの人が誤解や伝わらなさへの不安を持っているように思うし、コミュニケーションは失敗の連続だ。私自身も失敗は少なくない。例えば本書には、着物が似合う知人に「貫禄がありますね」と言ったら、褒めたつもりが「やっぱり太ったよね」とネガティブな意味で伝わってしまった失敗談を書いたりもしている。
わかり合えない不安が自分らしさの根拠
──本書の前提となるのが、言葉についての3つの見方です。
第1は、言葉は一義的な意味を伝達するための道具であり記号であるとする「論理的な見方」。第2は、言葉には含みがあり真の意味は発言者の感情の内側にあるとする個人的かつ「心理的な見方」。
どちらもわかりやすい見方だが、欠点もある。論理の世界(第1の見方)では人間の感情は切り捨てられる。言葉を個別の心理と単純に対応させれば(第2の見方)、今度はそれが「他人とはわかり合えなくて当然」という疎外感・孤独感につながってしまう。
そうした限界を乗り越えるのが、「言葉は〈場〉である」「言葉の意味は、相互作用によって生じる」という第3の「場の見方」だ。
──言葉の意味がその場その場で変わるということですか。
もちろん意味の核になる部分は変わらない。ただ、それが卵の黄身だとしたら、白身に当たる部分には、場の相互作用の影響をより受けやすいあいまいさがある。
そう難しい話ではなくて、例えば肯定的なはずの言葉が別の場では否定的なものに転じるなど、言葉の意味はしばしば変化する。普段意識することはないが、私たちは言葉を、過去の文化やコミュニケーションの蓄積から成るもの、個人の内面に閉じたものでなく、他者と共有する外部、相手と相互に影響し合いながら意味が定まっていくものとして使っているのだ。
共有のクラウドにある言葉を、都度ダウンロードして使うようなイメージをするとわかりやすいかもしれない。言葉のデータがクラウドに存在するだけでは何も起こらないが、使われ方、つまり場における相互作用によって意味の可能性が新たに生まれる。
さらに言うと、相互作用があって初めて「私」「あなた」「言葉の意味」といったものが出てくると私は考えている。
──相互作用が先にあってそこから個々の人格が生じる……?

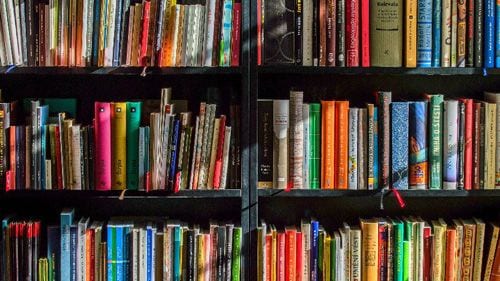































無料会員登録はこちら
ログインはこちら