
──『自分は「底辺の人間」です』、たいへん強烈なタイトルです。
青葉真司死刑囚(以下、青葉)が公判の中で自分の立場を表現する言葉として使ったものです。法廷で「京アニは光で、自分は影だ」と表現したように、青葉は京アニに憧れて近づきたいと思う反面、自らの生活は暗転して、社会の中で居場所を見つけられなくなってしまった。その中で自らを正当化する行動原理としたのが、「底辺の論理」。最終手段は仕返し、力でねじ伏せて黙らせる、というものです。
長らくこの事件を追う中で、こうした思考を持つ青葉自身は決して特殊な人間ではないと思うようになりました。社会の中ではい上がれずもがき苦しんでいる人は少なくない。第二、第三の青葉が出てきてもおかしくない。だが厳しい環境にあっても決して独りではない、社会の支えがある。それを伝えるために、象徴する言葉としてタイトルに用いました。
──就職氷河期世代でやはり不安定な生活を送ってきた男性は「事件はとんでもなく特別だけど、青葉はどこにでもいる人間。自分と彼とは紙一重だった」と言っています。取材班が見た青葉の素顔は。
初公判を傍聴した記者が漏らした感想は、「なんか普通の男でしたよ」でした。いわゆる「モンスター」ではなく、言葉も弱々しい。たまに饒舌(じょうぜつ)にしゃべるけど基本的にはおとなしく、法廷で罵詈(ばり)雑言をまき散らすタイプではなかった。
罪状認否では一言、「やりすぎた」と。36人が亡くなり、32人に重軽傷を負わせた男が、やりすぎたと反省めいたことを言う。公判は思っていたものとまったく違う展開になると自覚した瞬間でした。

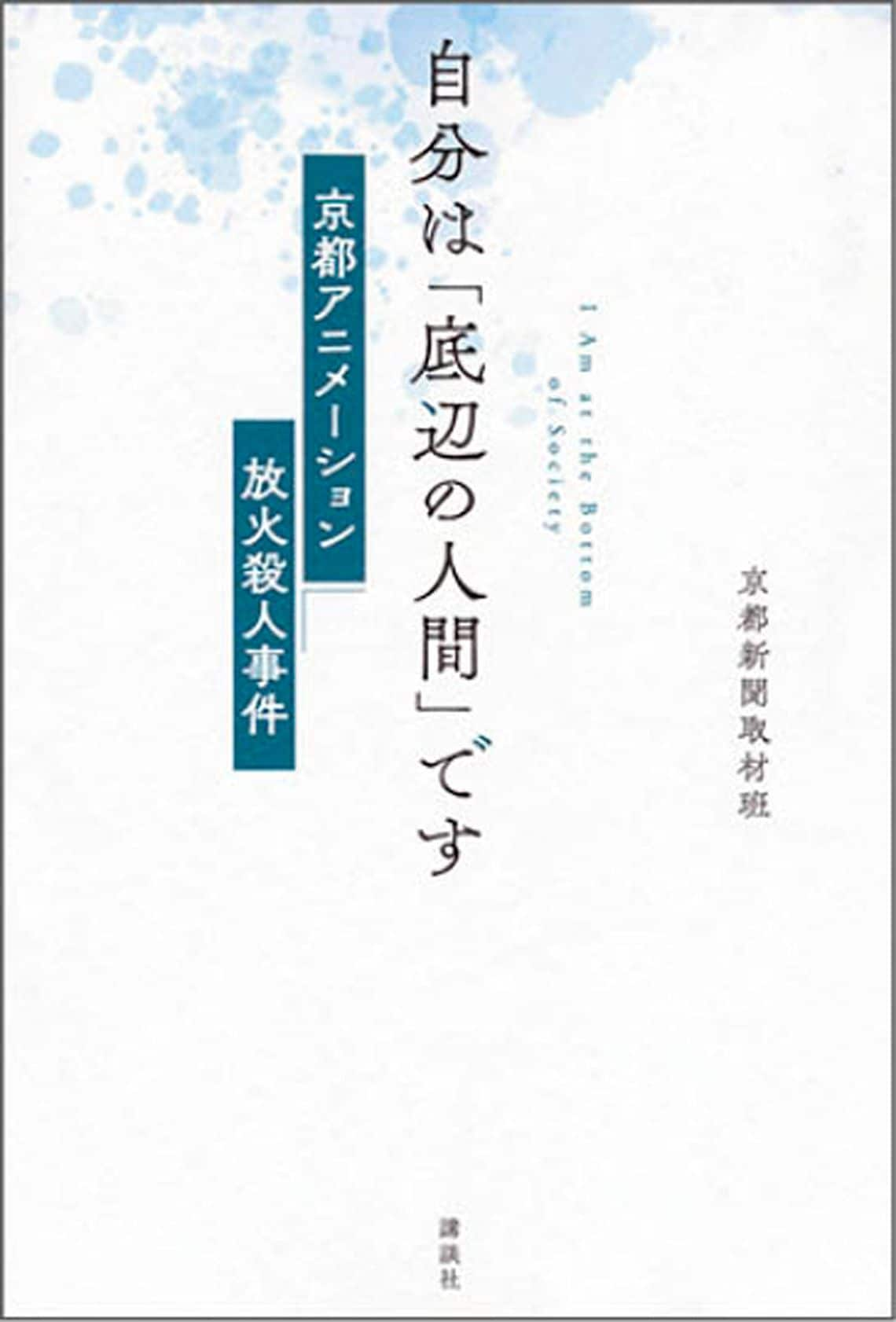
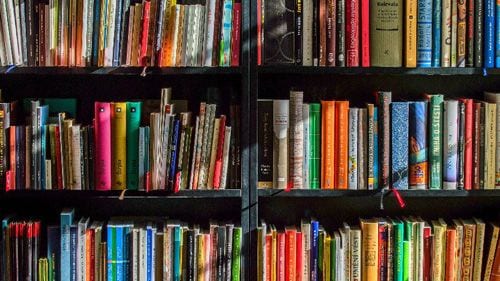

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら