
──本書は2014年出版の『基準値のからくり』の続編です。

前著出版のきっかけは11年の東日本大震災だった。東京電力福島原子力発電所の事故により、「ベクレル」や「シーベルト」など見慣れない単位が報道にも出てきた。ニュース番組では「基準値の○倍の量が検出されました」といった言葉が毎日のように使われた。
実は、「基準値の何倍」という数字から判断できることはほとんどない。だが当時、多くの人が基準値というものに関心を寄せ始めていることは、私の所属している日本リスク学会でも話題になった。中でも熱心な議論をしていた4人で本を書くことになった。
幸い前著は好評を博したが、この10年の間に、原発処理水、有害物質として規制されるPFAS(ピーファス、有機フッ素化合物)、パンデミックなど基準値と関係する新たなトピックが次々に出てきた。そうした動きを受けて立ち上げられたのが本書の企画だ。
4人各自がテーマを決め執筆を進めたが、一旦書き上がった原稿は論文の査読よろしくほかの3人からのコメントや指摘を受けて繰り返し、修正した。本書のために毎月約1時間のオンライン会議を1年以上続けた。

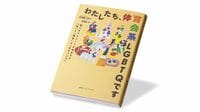
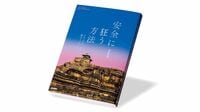
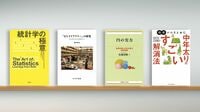
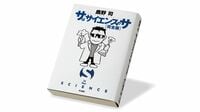



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら