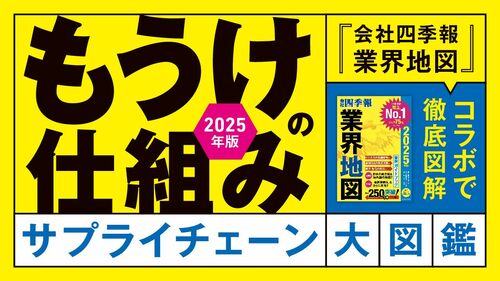薬製造の外部委託が増加

医薬品のサプライチェーンの出発点は、製薬会社の研究開発にある。どの疾患を対象とする薬を作るか決めた後、原料の調達や製造が始まる。原料は国内外から集まり、治験によって安全性や有効性を確かめられれば薬として承認され、市場に登場する。
新薬の開発には、10年以上の期間と数百億~数千億円規模の費用がかかるといわれている。国内最大手の新薬メーカーである武田薬品工業の研究開発費は年間7000億円超に上る。他社との開発競争の中では薬の革新性や開発スピードが問われるため、近年製薬会社は研究開発に特化し、製造などは富士フイルムホールディングス(HD)といったCDMO(医薬品の開発・製造受託機関)に委託するケースが増えている。
製薬会社は開発・製造の外部委託によって、研究開発コストや生産設備の維持コストを軽減できるメリットがある。外部委託は製造コストの低い低分子化合物がメインだった。だが、近年はバイオ医薬品といった開発・製造の難易度が高い医薬品が増えているため、CDMOにも高度な技術が要求されるようになっている。
製造された医薬品は、卸業者を通じて病院や薬局へ供給される。製薬会社の中にはドラッグストアなどで販売される市販薬を手がける企業もある。市販薬は医療用医薬品とは異なる商流で流通する。一部の製薬会社は直接販売ルートを持つが、大半の薬は卸業者を経由しており、医療用医薬品ではメディパルHDなど大手4社が国内市場シェアの8割を占める。
ここまで見ると薬のサプライチェーン構造は他業界とそれほど変わらないようだが、実は医療用医薬品には他業界とは大きく異なる特徴がある。薬価が国の制度で決められている点だ。