原材料価格やエネルギー費用の高騰、賃金の上昇が、あらゆる業界のサプライチェーンの持続性を揺るがしている。

(写真:OrangeBook / PIXTA)
企業がどこからどれだけ調達しているか。そしてどこに販売しているか。本特集では会社四季報記者が日頃の取材や産業連関表を基に、56業界のサプライチェーンを“見える化”した。

調味料や即席麺、菓子や飲料などの加工食品は、食品メーカーが製造している。だが、消費者が直接メーカーからではなく小売店で商品を購入するように、食品のサプライチェーンには多くの事業者が関わっている。
一般的に、食品メーカーは原料メーカーや商社からプラスチック製容器や植物油脂などを調達し、食品を製造・包装する。その後、多くの商品はいったん卸売業者へ送られる。各食品メーカーが小売店に商品を直接届けると、配達時間にばらつきが出るなど物流面で非効率的になるためだ。必要な商品を卸がまとめて配送・納品することで、最終的にスーパーやコンビニの棚へ商品が並び、消費者が購入できる。
トピックボードAD
有料会員限定記事

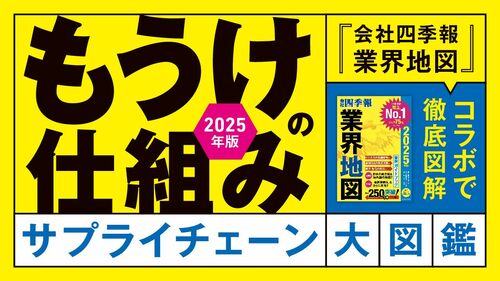

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら