独自のサプライチェーンの秘密に迫る。

神戸物産は、自社で生産するプライベートブランド(PB)商品を、フランチャイズ(FC)で展開する「業務スーパー」の店舗に卸売りする。食品スーパー業界では売上高営業利益率が平均2~3%にとどまる中、業務スーパー事業は7.6%の利益率をたたき出す。自社独自のサプライチェーンをどう築いてきたのか。神戸物産の沼田博和社長に聞いた。
──神戸物産はなぜ製販一体に着目したのでしょうか。
創業者である父(沼田昭二氏)が、ナショナルブランド(NB)商品を扱う既存の食品スーパーとの差別化のために考えたビジネスモデルだった。企業の規模と購買力では既存大手の食品スーパーに勝てないし、仮に同じ商品を売ってもどちらが安いかと泥仕合をしている限り儲からない。
そこで、独自色を出しながら安くてよい商品を提供するために、食品製造業に活路を見いだした。業務スーパー1号店は、集客性は乏しくても低家賃で借りられる立地に出店した。アクセスしづらくても消費者に足を運んでもらえるように、PB商品が始まった。
ウォルマートから着想
──食品スーパーのビジネスは製販一体でどう変わりましたか。

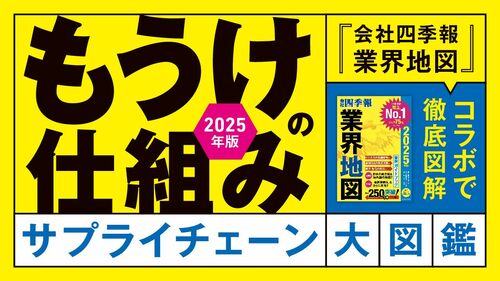































無料会員登録はこちら
ログインはこちら