米中対立など地政学リスクの高まりを受けて、サプライチェーンを経済安全保障の観点から見直す動きが加速している。
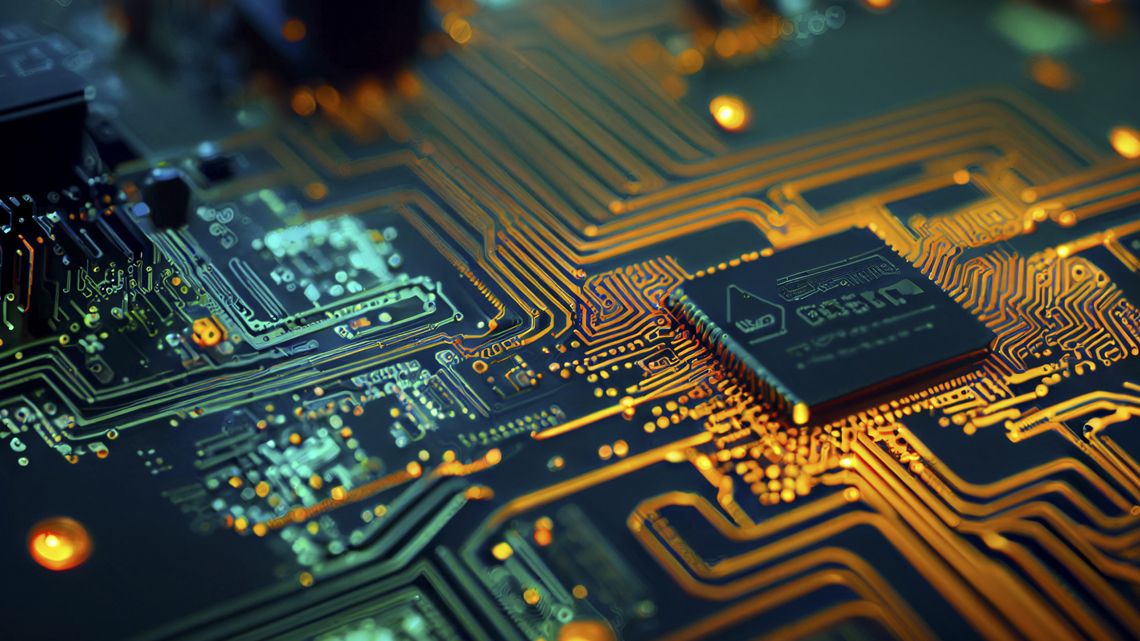

半導体業界のサプライチェーンは、水平分業が徹底されていることで知られている。半導体チップの設計・開発から製造、そしてスマートフォンなどに搭載できる形に仕上げるまでの工程それぞれで分業体制が敷かれている。
かつて栄華を誇った日立製作所やNECなど日本の半導体メーカーは、これらの全工程を担う垂直統合型だった。現在では、このモデルを採用する大手半導体メーカーは、米インテルや韓国サムスン電子などに限られる。米エヌビディアなど大手半導体メーカーの大半が、自社工場を持たないファブ(工場)レスのモデルを採用し、設計・開発のみを担っている。
高度な分業体制
実際のチップ製造は、台湾のTSMCに代表される、製造受託企業(ファウンドリー)に発注することになる。ただ、ファウンドリーですら仕上げの最終工程までを一手に担っているわけではない。製品として仕上げるためには、ファウンドリーもまたOSATと呼ばれる仕上げ専業の企業に発注することになる。
半導体は、設計・開発から製造まで最先端技術の結晶だ。各工程での投資を1社で担うのは非効率なことから、こうした高度な分業体制が築き上げられてきたのだ。
加えて見逃せないのは、半導体サプライチェーンにおける日本企業の重要性だ。凋落して久しいといわれる日本の半導体メーカーだが、今なお世界トップクラスの存在感を誇る領域がある。半導体製造に欠かせない、半導体製造装置や材料の分野だ。

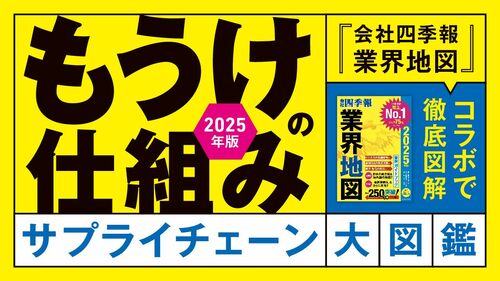
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら