原材料価格やエネルギー費用の高騰、賃金の上昇が、あらゆる業界のサプライチェーンの持続性を揺るがしている。


衣食住の「衣」を担うアパレル産業。私たちの生活と切り離せない衣服は、どのようなサプライチェーンをたどって消費者の元に届くのか。
アパレルのサプライチェーンは、原材料から販売に至るまで工程ごとに分業されているのが特徴だ。繊維・テキスタイル(布)のメーカーが素材を作り、染色加工会社が染色を施す。その後、縫製会社がボタンやタグといった副資材と生地を合わせて縫製し、1着の服が完成する。出来上がった商品は百貨店や専門店・量販店などの小売りに卸され、消費者の手に渡る。
専門商社はこうした原材料・加工企業や縫製工場とのネットワークを持ち、商品を企画するアパレルメーカーにつなぐ役割を担う。メーカーでも三陽商会のように自社工場で技術を蓄積し、品質管理を手がけることもある。
従来の分業構造に限界も
一方で、そうした水平分業型のサプライチェーンでは、最終消費者からは離れた上流の素材メーカーが開発した素材を起点に毎シーズンの商品開発が行われるため、変化が激しいトレンドや消費者ニーズを的確に捉えて対応することは難しい。
また、アパレルの水平分業型の商流では、生産や流通の各工程で中間マージンが確保されるように商売を組み立てる。そのためサプライチェーンの中で利益が分散し、小売店は薄利の商売を受け入れざるをえない構造になっていた。

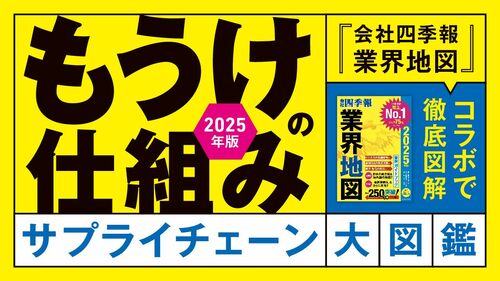

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら