少子高齢化や人口減少によってサプライチェーンの形を見直す業界が少なくない。最前線の動きとは。

製粉|政府が小麦の輸入価格を決める

小麦の約9割は海外からの輸入だ。安定供給のため政府が全量を買い付け、製粉会社に売り渡す。日清製粉グループ本社(2002)やニップン(2001)といった製粉会社は、小麦粉を用いた食品を販売するほか、食品メーカー向けにパンや麺など用途に応じて加工・販売している。
政府の売り渡し価格は半年に1回改定される。ウクライナ戦争で小麦の価格が高騰したことで、2023年前半には1トン当たり史上最高の7万6750円まで上昇。24年後半でも6万6610円と高止まりしている。小麦粉の価格は政府の売り渡し価格に連動するが、これまでは売り渡し価格の上昇に価格転嫁が追いつかないこともあった。
各社はコスト削減や高付加価値品の開発に取り組む。近年、臨海型の大型工場を建設する動きが加速。日清製粉では25年に水島工場(岡山県)が稼働する。ほかにも、パスタ類の開発ではゆで時間の短縮や食感の改良を進めている。

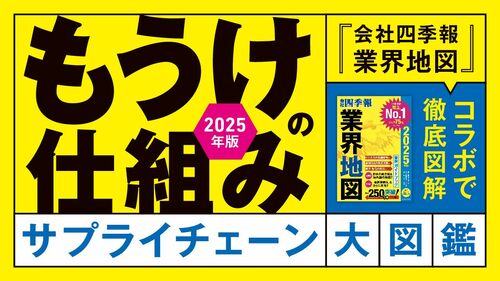

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら