
今回も、前回の「豊洲問題の"紛糾"は『現代型組織』の必然だ」に引き続き、会社や官庁などの組織と哲学的「よさ」について考えていきたいと思います。もっとも、私はそうした組織に勤めたことはなく、よってその「空気」はまるでわからず、どうにか想像してみるだけなのですが、それでも、批判する権利はあるように思います。
私の父はサラリーマンでしたが、頑固一徹で会社の「世話になること」を蛇蝎のごとく嫌い、会社のセロテープですら私用で使うことを嫌がった。お中元もお歳暮も禁止。たまに贈られてくると、苦い顔をして勤務評定の評価を下げていた、と聞いたことがあります。

そんな父の「要領の悪さ」に対し、母は「よくそれで部長になれたものだ」とひどく嫌っていました。しかし、父は断じて譲らず、会社の人間は誰も家に呼ばず、しかも仕事の話は家で一切しないのですから、私もまったく会社とはどういうところかわからない。
以上はただの「枕」ですが、私はその父の血を受け継いでいて、少年のころから会社でだけは働きたくないと思っていた。当時はまだ高度成長前(さしかかるころ)で、サラリーマンとは「気楽な家業」というイメージが定着していた。私はその“のんべんだらり”とした村社会的雰囲気を恐れていたのでしょう。
あらゆるホンネが潰される「会社」になぜ勤める?
大学に入ってすぐに、京極純一教授の「政治学」の講義で、日本政治思想史について学んだのですが、教授が挙げる参考書を読んでみると、丸山真男や神島二郎などの碩学も日本社会を徹底的に批判していた。そこは、馴れ合いと談合が支配し、個人は「和」の名の下に抹殺され、あらゆるホンネは潰され、あくまでもタテマエがまかり通り…という話がどこまでも続く。そして、その日本型村社会の典型が会社であり、官庁であることも当然のように触れられる。私はこういう講義を聴いて、皆なぜそんなヒドイところに、しかもある程度の希望をもって勤めようとするのか、不思議でならなかった。


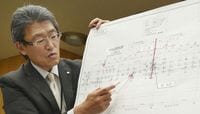






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら