
「不機嫌ハラスメント」という言葉を聞いて、正直驚いた。
最近は「フキハラ」などとも呼ばれ、SNSでも頻繁に目にするようになった。確かに職場で不機嫌な人がいると空気が重くなる。しかし、それを「ハラスメント」と定義していいのだろうか。人間は感情の生き物だ。どんなに優秀な人でも、プライベートの事情や体調不良で不機嫌になることはある。それを一律にハラスメント扱いすることに、私は強い違和感を覚える。
そこで今回は、不機嫌ハラスメントの正しい捉え方と、不機嫌な部下への接し方について解説する。部下のマネジメントに悩んでいる管理職の方は、ぜひ最後まで読んでもらいたい。
不機嫌は本当にハラスメントなのか?
まず押さえておくべきは、ハラスメントの定義である。
厚生労働省が定義するハラスメントには、明確な要件がある。パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、マタニティハラスメント——いずれも「優越的な関係を背景とした言動」「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」「労働者の就業環境が害されるもの」という3つの要件を満たす必要があるのだ。
この定義に照らし合わせると、単に「不機嫌である」という状態は、ハラスメントの要件を満たしていない。
不機嫌な態度が継続的で、特定の人物に対して威圧的に振る舞い、その結果として相手が精神的苦痛を受けているなら話は別だ。しかし、ただ機嫌が悪そうにしているだけでは、法的にハラスメントとは認定されない。

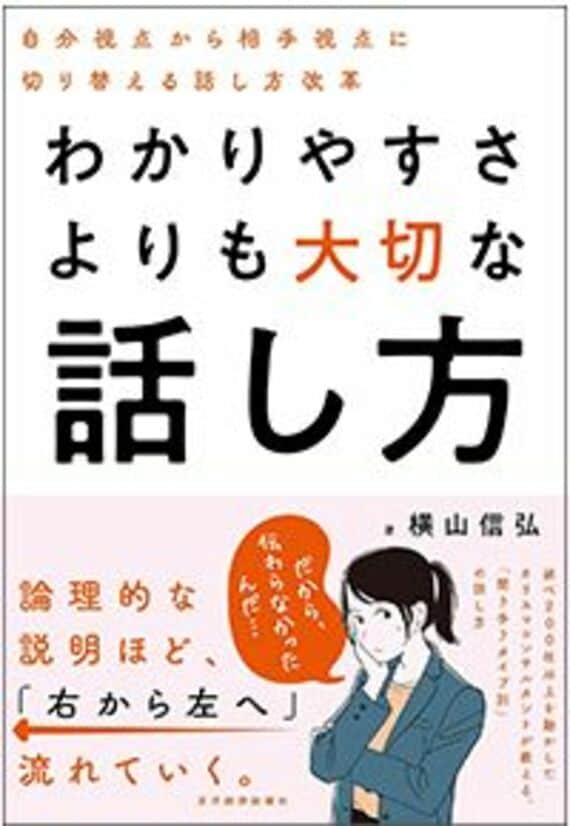






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら