いつしか季節は秋になっていた。
だれのせいでもない、自身の恋のせいであれこれともの思いにふけることが多く、光君が左大臣家に行くのも途絶えがちになり、左大臣家では恨めしく思っていた。
六条の女君にしても、熱心に口説いていた頃のような気持ちには戻れずに、あたりさわりのない扱いしかできずにいては、女君も不憫(ふびん)である。
……関係を持つ前に執心したように、何がなんでも逢いたいという一途(いちず)な気持ちが消えたようなのは、いったいどういうことなのでしょう。
六条の女君は、何についても深く思い詰める性分だった。年齢も自分のほうがずいぶん年上で、そもそも不釣り合いなのだし、もし二人の噂(うわさ)が世間の人の耳に入ったらいったいどんなふうに言われるか。光君が逢いにこないさみしい夜に、ふと目を覚まし、女君はいっそうくよくよと思い悩んでは、悲しみに打ちひしがれるのだった。
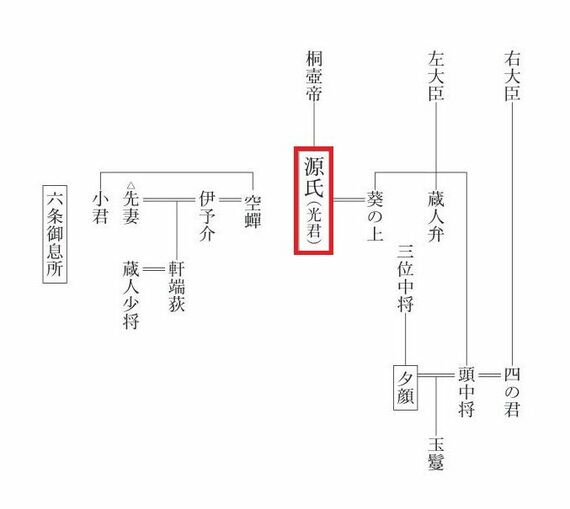
手折って我がものとせずにはいられない
霧の深いある朝のことである。暗いうちに帰るようにしきりに急(せ)かされ、眠たそうにため息をつきながら帰っていく光君の姿を、女主人にひと目見せたいと思ったのか、女房の中将の君は格子(こうし)を一間だけ上げて几帳(きちょう)をずらした。六条の女君は頭をもたげて外を眺めやる。色とりどりに花の咲き乱れている植えこみを、光君はしばらく眺めている。その姿は、類いまれなほどのうつくしさである。車に乗るため廊に向かう光君を、中将の君が送っていく。季節にあった紫苑色(しおんいろ)の表着(うわぎ)に、薄絹の裳(も)をすっきり結んでいる腰つきも、しなやかで優美である。光君は中将の君をふり返り、隅の間の高欄(こうらん)に座らせた。彼女の、たしなみのあるかしこまった態度や、黒髪の下がり具合も、さすがに気品があると光君は思う。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら