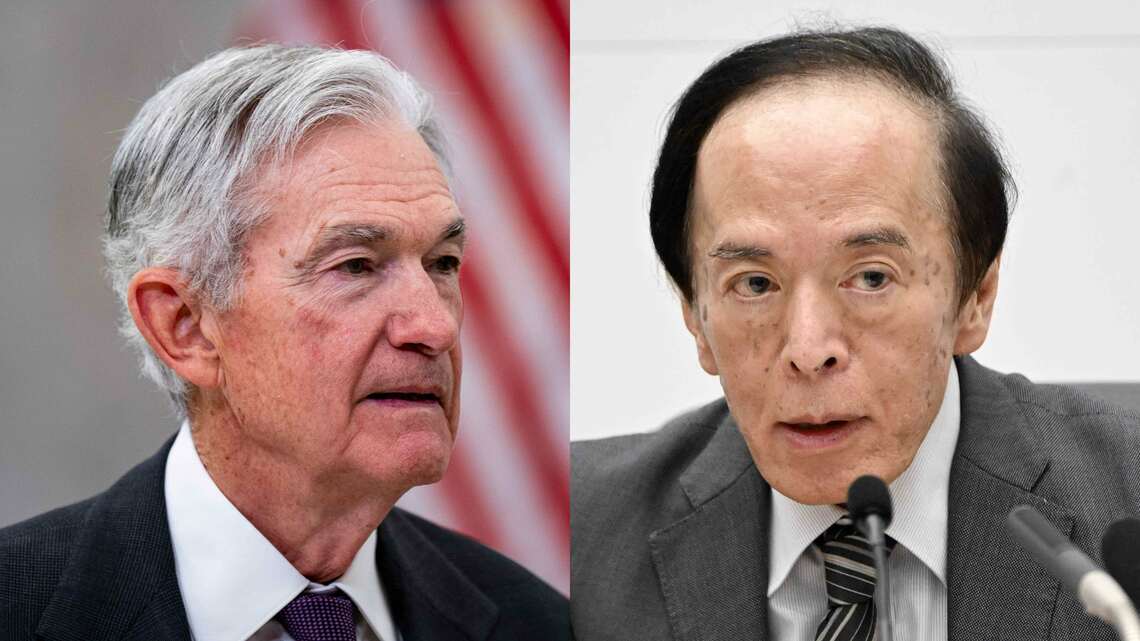
「参議院選挙」と「日米関税交渉」という市場にとっての2つの大きな不確実性は一応の決着をみた。
参議院選挙は、国民民主党や参政党など若者や就職氷河期世代の不満や不安にフォーカスした政党が大幅に伸びた一方、財政規律や社会保障制度の持続性を他の政党に比べ相対的に強く訴えたと映った与党が議席を減らし、衆議院に続き参議院でも少数与党に転落した。また、野党の中でも財政規律を重視していると映った立憲民主党は議席が伸び悩んだ。
こうしてみると、選挙の争点は「給付か、減税か」という政策の手法ではなく、積極財政の強度を競ったものであったといえる。
本格的な財政ポピュリズムが到来
有権者に訴えるロジックも変化した。これまでMMT(現代貨幣理論)などを根拠に積極財政を唱えた政治家は一定数存在したが、そんな理屈に頼ることなく、「税収が上振れしたから税収を国民に戻せ」「生活が苦しいから消費税はゼロにせよ」といった直感に訴える主張が席巻した。これは有権者へのアピール方法として一つの「発明」とすら感じる。
また、想定以上のスピードで進む少子化で、ただでさえ年金制度の持続性が大きな懸念になっている中、「手取りを増やすために社会保険料を下げる」というわかりやすいロジックで議席を大きく伸ばした政党もあった。こうした主張に対しては、年金制度や健康保険制度をどう変えると社会保険料の引き下げが実現できるのかという疑問が当然のように沸くが、どの党も議論に深入りするのは得策でないと考えたのか、詰めた議論を仕掛ける政党は最後まで出なかった。
有権者の判断基準が目先の損得といった短期志向を強め、いよいよ本格的な財政ポピュリズムが到来したように感じられる。選挙後、長期金利は上昇している。

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら