困惑した朴は、教授に尋ねた。
「このプロジェクトのゴールはどこで、僕は何をしたらいいんですか?」
返ってきた答えは、「自分で考えなさい」。
プロジェクトのメンバーは、朴と下級生がひとり。大学院で何をするのかもよくわかっていなかった朴は、与えられた任務の責任の大きさだけを実感し、無我夢中で動き始めた。
大学院では「隣の研究室は外国よりも遠い」と言われているそうだが、そんなことを知る由もない朴はロボットの研究室、物理の研究室など気になる研究室を訪ねては、そこの教授に「どうしたらいいんでしょう?」と相談。このときに築いた横のつながりが後になって生きてくるのだが、朴自身は暗中模索が続いた。その間、梅津教授は人工心臓の開発で長年連携してきた日本のトップレベルの心臓外科医たちに、朴を紹介して歩いた。
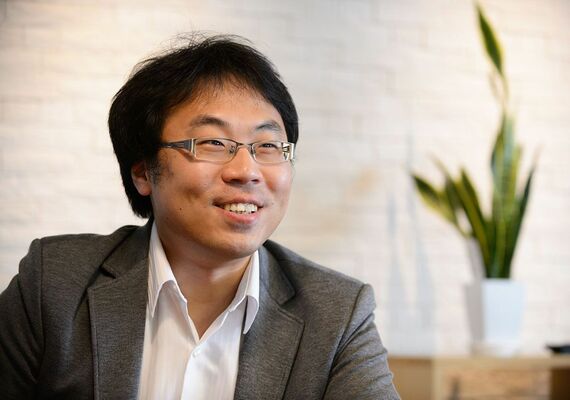
「彼はこれから患者ロボットを開発するので、ひとつよろしく!」
世界的な権威の梅津教授がわざわざ連れてくる教え子となれば、どの教授も興味を持つ。
「なるほど、君はいったいどういうものを作ろうとしているんだね?」
そう尋ねられた朴は、まさか何のメドも立っていないと明かすこともできず、冷や汗をかきながら「これからいろいろ考えるので、まずは現場が見たいんです」と訴えた。額を流れる汗が功を奏したのか、その後、名だたる教授たちが朴の研究を後押ししてくれるようになった。
そうして心臓外科医の現場に足を運ぶようになって知ったのが、臨床業務と雑用に追われ、ろくにトレーニングをする時間もない中で、豆腐やナプキンを縫ってなんとか心臓血管縫合の技術を向上させようとする若手の医師の苦悩だった。
これだ! と朴は確信した。
「手術は膨大で複雑な不確定の要素の中を何とか乗り切るもので、心臓血管の縫合はその過程の一部に過ぎません。しかし、とても重要なピースで、決して無視はできない技術です。それだけに、こんなものでトレーニングしてるんですか!? という驚きはありましたが、それよりも、困った人がいたら助けたいという自分の原点に火がつきました」
思い立ったら、即、行動する朴は、まずリアルに拍動する心臓のモデルを作った。きっと何かの役に立つだろうという期待があったが、医師たちからの評判はさんざんだった。
「面白いけど何のトレーニングにもならないし、何なのこれ?」
これじゃあ、ダメだ……。朴は手応えゼロの失敗に、唇をかみしめた。ちょうど大学院の1年目が終わった春だった。
通学途中に舞い降りたアイデア
何を作ったらいいのか、何が求められているのか、何が役に立つのか。先が見えない研究のことで朴の頭の中はいっぱいだった。そんなある日のこと。
いつも月島の実家から自転車で有楽町まで行き、JRで高田馬場の大学に通っていた朴は、その道すがらにあるスッポン堂の前を通り過ぎたとき、まるで脳天を雷に撃ち抜かれたかのように、アイデアがひらめいた。
イメージは、ハード1台あれば無数のソフトで遊ぶことができるファミコンだった。これまでのトレーニング装置はマネキンに模擬心臓を組み込んだような一体型で、高額なうえに気軽にトレーニングできなかった。それなら、ファミコンと同じように心臓の拍動を表現するマシンに、血管モデルを簡単に着脱できるトレーニング装置を作ったらどうだろう。マシンはハードとして大学に買ってもらい、血管モデルはいろいろな種類の血管を組み込めるような形で量産すれば、数千円の価格帯にできる。
ファミコンが楽しい理由は、順位や点数が出るからだ。スコアが出れば、それまで自己満足でしかなかった手技が客観的に評価される。いかにうまくなったのかを科学的に検証できる。
ハード、ソフト、評価を連動させる形で作れば、それを一体運用してトレーニングする仕組みやカルチャーそのものを世界に提示することができる――。あまりにも明確なビジョンに興奮した朴は、すぐにシリコンに模擬血管を埋め込んだ試作品を作り、梅津教授のもとに駆け込んだ。

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら