部下から上司への「逆パワハラ」はなぜ起きる? 「声が小さい!」と叱咤、SNSに中傷…。逆パワハラされる"召使い上司"の惨状とは
なぜ近年、部下から上司への逆パワハラが増加しているのか。主な原因は次の3つだろう。
それでは、一つ一つ解説していこう。
逆パワハラが増える3つの原因
(1)過剰なハラスメント防止の流れ
1つ目の原因は、パワハラを過剰に意識する上司が増えたことだ。
近年の改正労働施策総合推進法(改正パワハラ防止法)の施行に伴い、企業はハラスメント対策を強化している。その結果、上司が部下に指導を行う際には「発言の一言一句がパワハラにならないか」と注意を払わねばならなくなった。
ある製造業の部長は「社内の通報制度ができてから、部下への指導のたびに録音されてるかも」と恐怖を感じるとぼやいていた。言葉の一つ一つに神経をすり減らし、そのせいで明確な指示が出せなくなっている。
(2)心理的安全性の誤解
2つ目の原因は、心理的安全性を重視するあまり、組織の「フラット化」が進められたことだ。経営者が「何でも言い合える職場」を宣言した結果、部下は思ったことを遠慮なく言えるようになった。
ただ、この心理的安全性が悪用されている例も増えている。ある会議では「課長の指示通りにやれば本当にうまくいくんですか?」「ダメなら罰金払ってもらえますか?」といった、単なる上司否定としか思えない意見を出すケースも見られる。
(3)仮説思考の欠如
3つ目の原因は、仮説思考を欠如した人の増加だ。そのような人が増えると根拠を伴わない反論や提案が乱立し、組織の合意形成が困難になる。
たとえば部下が十分なデータや事例を示さずに「そんなシステムに投資するより、給料を増やしたほうがみんな喜びますよ」「そういった部長の方針が、私たちのやる気をなくすんです」と迫る。このため、上司はいちいち部下を説得しなければならなくなった。
しかし、うまく説明できない上司に部下は従わない。昔のように「いいからやれ」「やればわかるから」という上司の一言で、とにかく従わざるをえなかった時代ではないのだ。
これら3つの要因が重なり合い、かつては考えられなかった「部下から上司への過激な言動」が増加しているのではないだろうか。
みんながみんな、そうではない。だが上司が"支援型リーダーシップ"を発揮しようとすればするほど、部下の要望はエスカレートし、ついには威圧や嫌がらせにまで発展するケースもあるのだ。













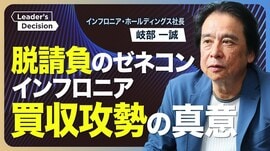

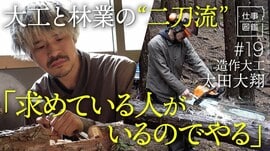





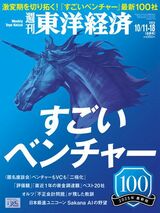









無料会員登録はこちら
ログインはこちら