部下から上司への「逆パワハラ」はなぜ起きる? 「声が小さい!」と叱咤、SNSに中傷…。逆パワハラされる"召使い上司"の惨状とは
ある部長は、部下からの相談や要望に真摯に耳を傾ける日々を送っていた。しかし「会議で声が小さい」「もっと上司らしく指示を出して」と繰り返し叱責されるようになった。
プレゼン資料を事前に共有しても「読みづらい」「わかりづらい」と難癖をつけられる。最終的には部下数名が結託し、「上司の指示がサイアク」と社内SNSで訴えかけた。
訴えを見た上層部は、部長がパワハラをしているのではないかと考え、部長を一時的に減給処分とした。この事例は、指導よりも奉仕を優先した上司が、エスカレートする部下からの要求に対抗できず、逆に攻撃の対象となってしまった典型だ。
"召使い上司"を大量増産する会社2つの特徴
部下への過剰な"奉仕"をしてしまう上司――"召使い上司"を大量輩出してしまう会社はどんな特徴があるのか? 主に、サーバントリーダーシップとティール組織、この2つを信奉している会社が多いと筆者は考えている。
(1)過度な奉仕スタイル
近年、サーバントリーダーシップ(支援型リーダーシップ)が日本でも普及している。
サーバントリーダーシップとは、リーダーが命令や指示を最優先せず、部下の声に耳を傾けるスタイルのことだ。サーバントとは、使用人、召使いの単語からきている。傾聴や共感、働きやすい環境整備で成長をサポートする考え方だ。
以前は「支配型リーダーシップ」をしていた上司が、一転して「命令よりもサポートを」と教育されると、どうしたらいいかわからなくなる。その結果、自分の裁量を放棄し、部下の主張に同調しすぎるようになる。
ある会社では「マネジャーは部下の雑用係ではない」と言いながら、実際には「部下から何か言われたら、すべて聞くのがサーバントリーダーシップだ」という誤ったメッセージが発信され続けた。
その結果、上司たちは部下からの無理難題にも「イエス」と言い続けた。ついには自分の判断で何も決められない「召使い上司」へと成り下がった。
(2)ティール組織の導入押しつけ
同じように、ティール組織のスタイルを全社に導入した会社も多い。
ティール組織とは、社員一人ひとりが自律的に意思決定し、互いの個性や全体性を尊重して働く組織形態のことだ。階層を減らして権限を委譲する。そして組織の目的に沿った自発的・柔軟な行動を促進する組織モデルである。
ボトムアップ型の組織とは違う。階層そのものをなくすことが基本的な考え方だからだ。
しかし、チームがまだ未成熟なのに組織の「フラット化」を強引に進めるとどうなるか? 組織リーダーが柔軟に制御できればいいが、そうでないとマネジメントしづらくなる。
ひどいケースでは、「何でも自分たちで決める」と部下が言い出し、上司の助言をことごとく無視。大きなトラブルが起きたときは、「上司のサポートが足りなかった」と責任転嫁する。こんな事例が実際に起こっているのだ。














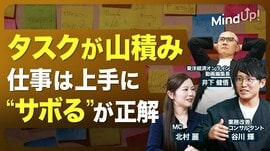

















無料会員登録はこちら
ログインはこちら