部下から上司への「逆パワハラ」はなぜ起きる? 「声が小さい!」と叱咤、SNSに中傷…。逆パワハラされる"召使い上司"の惨状とは
現場に入ってコンサルティングをしていると、非常に気になるのが「流行のスタイル」に飛びつく会社が多いということだ。多様性の時代である。人の価値観も考え方も多様だ。どんなシステムも、どんなスタイルも、すべての組織に馴染むことはない。
サーバントリーダーシップやティール組織の考え方は、組織の成熟度や文化に合わせて段階的に導入すべきだ。そのためにも、何より継続的な教育が必要である。
「若い人の感性が大事」
とはいえ、そのテーマ(経営やマネジメント、マーケティング、商品開発等)について詳しく知らなかったり、仮説思考もなかったりするのであれば、彼ら彼女らの意見は受け入れがたい。次のパターンを見てもらいたい。
かつては(1)(2)ばかり採用され、(3)(4)は無視される組織が多かった。しかし現代は、心理的安全性を高めようと、(3)も(4)も無視されないようにする組織が増えている。
とはいえ、もちろん会社が採用するのは(1)や(3)である。"当てずっぽう"な意見や主張である(4)は、昔と変わらず受け入れられないのだ。
上司もそのことを、しっかり認識することだ。そして毅然とした態度をとるようにしよう。
「私は強く言えないタイプだから、サーバントリーダーシップを発揮したい」
などと安易に決めないこと。リーダーシップのスタイルは、自分の性格で決めるのではない。部下の考え方やレベル感で使い分けるものだからだ。自分視点でもなければ、世間の流行の視点でもない。あくまでも他者視点で、必要な仕組みやスタイルを選ぶことだ。
「相手の立場に立って考える」
奉仕と自律のリーダーシップ、組織形態は、たしかに組織を強くするための有効な手法である。
しかし、導入の手順を誤れば、部下からの逆パワハラにつながりかねない。"召使い上司"にならぬよう、組織文化や部下のレベル感を見極め、段階的にスタイルを選択するようにしよう。
「相手の立場に立って考える」ことがビジネスの基本なのだから。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら














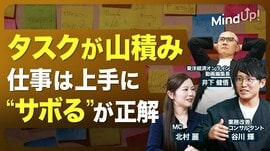

















無料会員登録はこちら
ログインはこちら