「触れてはいけない存在」昭和天皇崩御が露わにした日本社会の構造
原 たとえば肉声。昭和天皇の肉声には独特な抑揚があった。玉音放送のあの有名な抑揚です。たとえ人間宣言をしてもそういう身体性はもちろん変わらないわけで、晩年になってももちろん変わらない。正月二日の一般参賀のときに国民の前に現れて「今年もよい年であることを希望します」と言う身体と、玉音放送で「耐え難きを耐え……」と言う身体は変わらない。
実は国立国会図書館の職員だった1986(昭和61)年に、国会職員の特権で一度だけ開院式に臨んでおことばを読み上げる昭和天皇の肉声を生で聴いたことがあるんです。なんというか、あの肉声の感じはちょっと只者ではない。それが代替わりして、急に声が軽くなった感じがしたわけじゃないですか。それで平成の天皇は最初、ものすごく評判が悪かった。
奥泉 そうでしたっけ?
原 はい。いまやほとんど忘れられていますが、どうしても昭和天皇と事あるごとに比較され、重々しさがないと言われたのです。
奥泉 それを言ったのは主に右派の人たちではないですか?
原 明治から大正に変わったときに似ていると思いますが、「軽い」とか「存在感がない」とか、右派に限らず、一般的な印象としてあった。うちの父親なんかも言っていましたからね。要するに天皇といえばどうしても昭和天皇のイメージなのです。しかも大正期と同様、皇后の存在感が大きくて、その分、天皇の存在感が相対的に小さくなった。昭和が当たり前と思っていた人にとっては大きな違和感があったと思うんですね。
オウム真理教から派生した団体「ひかりの輪」の副代表で、昭和天皇が死去した1989年1月7日にオウム真理教の信者になった広末晃敏(ひろすえ・あきとし)は、「まだ当時は認識していませんでしたが、天皇崩御によって生じた心の空隙を埋めるために入信した私は、潜在意識下で、天皇の代わりを麻原〔彰晃〕に求めたのかもしれません」(「私が起こしたオウム事件──オウム・アーレフ18年間の総括」、ひかりの輪ホームページ)と回想しています。オウム事件の遠因は昭和天皇の死去にあったとも言えるわけです。
もう一つ決定的なのは、1991(平成3)年、雲仙普賢岳(うんぜんふげんだけ)の大火砕流の直後に天皇・皇后が日帰りで長崎まで飛行機で往復し、島原の体育館で二手に分かれて被災者にひざまずいて話しかけたという、あの場面だったと思います。明らかに昭和とは違う、平成の光景ですよね。
流通しはじめた新しい天皇のイメージ
奥泉 たしかにあのあたりから、新しい天皇のイメージが流通しはじめましたね。昭和には天覧という言葉があった。長嶋茂雄がサヨナラホームランを打った後楽園球場とか、大相撲とか。つまり天皇の来臨には、戦前から続く何かしらの特別感があった。平成はそういう感じではなくなる一方で、平成の天皇はべつの方向への聖性の獲得に向かったと言えそうですね。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら





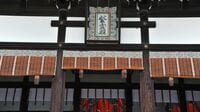


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら