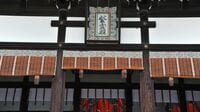「触れてはいけない存在」昭和天皇崩御が露わにした日本社会の構造
ほかの全国紙は地方にいる記者を呼び寄せてにわかに宮内庁担当の数を増やしたりしていた。日経にはそんな体力はないので、私のような1年目の記者の負担が一番重くなるわけです。たまったもんじゃないですよ。他社の3人分くらいをこっちは1人でやっている。体が持ちません。そういう、ある意味では壮絶な体験をしました。
奥泉 なるほど。たしかにあのとき、王の身体が日本という国の時空間を支配している現実が浮かび上がった気がしました。普段は意識しなかったことです。天皇のことなど全然考えないで毎日暮らしていた。ところが天皇の聖性はなお生きていた。戦前戦中にあった現人神としての天皇の聖性は、戦後の「人間宣言」を経てなお、戦後にも持ち越されてきたと考えていいんでしょうね。
原 そうですね。
天皇崇拝の構造
奥泉 一君万民のイデオロギーをリードした戦前の中間層に対して、1960年代以降は天皇制否定を基調とする新しい中間層が生まれていた。戦前と戦後はかなり対照的だと言えますが、実際に天皇制はなくなったわけではない。とはいえ、天皇の帯びる聖性は薄れていっていると感じていたんですが。
原 当時、社会部のデスクだった人たちは、1968(昭和43)年か69年くらいに新聞社に入った世代でした。当時はまさに大学が一番荒れた時代です。だいたい学生運動を大学でやっていて、一般企業はどこも採用してくれないから新聞社を受験して入ったという人が多かったのをよく覚えています。だから当然、反天皇が根底にある。なんでこんなことをやらなきゃいけないんだ、往生際の悪い奴だな、などとぶつぶつ言いながらやっていた。新聞社としては自社だけが特オチというのは完全な失態になるからしかたなく行きますが、だれも進んではやっていなかったのです。
奥泉 そこが興味深いところですよね。昭和天皇は戦後の行幸でものすごく人を集めた。戦前と変わらぬ熱狂的な天皇崇拝の場が出現した。それはそうだと思います。しかしその人たちが家に帰ってどうだったか。家に帰ったら全然違うことを言っていたのではないか。公の場面では天皇を崇拝しているかのように振る舞うが、反天皇制の思想を抱く新聞社の人たちが「なんでこんなことしなきゃいけないんだ」と思いながらも、社員の役割としては天皇の病状を仔細に伝えなければならないと考えるのと同じような意味において、ある制度の枠内で、天皇崇拝というものは表現されてきたのではないか。