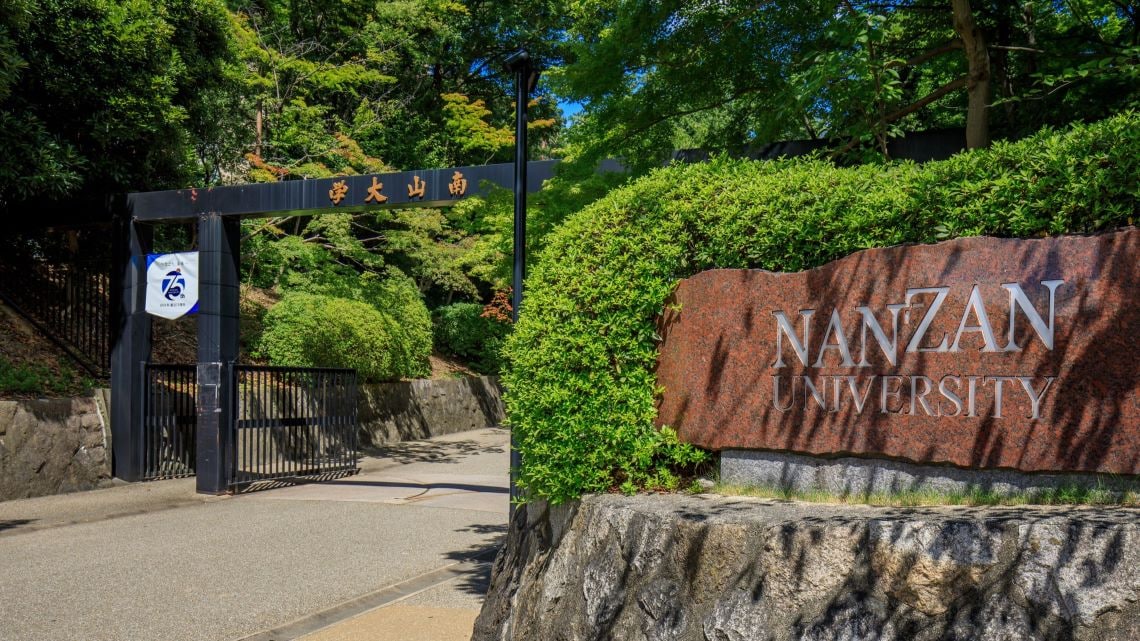
続いては中部地区。下図は、10年先の大学序列と併願先を弊社が全国300塾に行った調査を基にして地域別に示したものだ。
10年後に予想される大きな変化
現在、国公立では名古屋大、私立では南山大が頂点(厳密には理系は名城大学がトップ)を形成している。10年後に予想される大きな変化といえば、南山大が下落すること。よって、3の大学群はどんぐりの背比べ状態になる。
このエリアの受験生の悩みといえば、関関同立(関西大学、関西学院大、同志社大、立命館大学)、GMARCHレベルの私立大学がないことだ。
このため、現在、高学力層は関西や首都圏の難関私立大学に流れるが、それがさらに進行する。1のいわゆるトップ国公立大学群の志願者は、3より関関同立、GMARCHを積極的に併願するようになるだろう。なお、未掲載だが、豊田工業大学は3のワンランク上に存在している。
1は早慶、2は関関同立、GMARCHの併願合格率がそれぞれ下がる。2の大学群のうち、少子化の影響で新潟大、金沢大、信州大学の序列が低下、愛知県立大学などと序列が逆転しそうだ。
3は理系学部が名城大を除き弱い。その隙を狙って、5の中部大学などが食い込むとみられる。
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら