中学序列に崩壊の兆しあり。
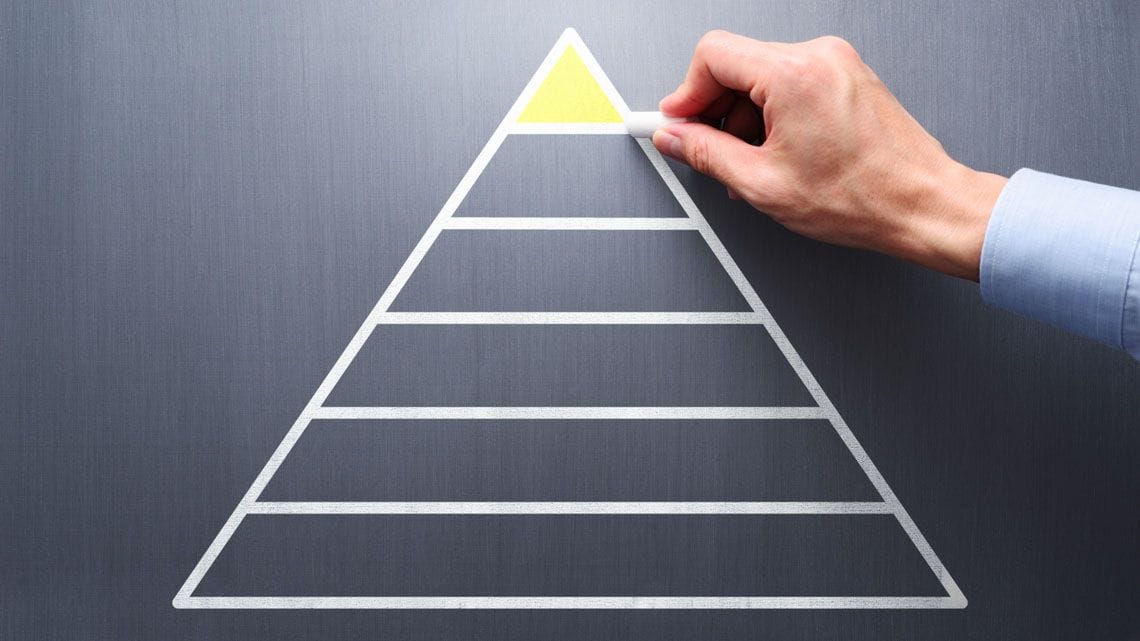
(写真:tadamichi / PIXTA)
何が何でも中高一貫校――。首都圏では小学校6年生の児童数が大きく減る中、中学校の受験者数が過去最多を更新しそうな勢いだ。なぜなのか。
『週刊東洋経済』2月3日号の第1特集は「過熱! 中学受験狂騒曲」。パニックの様相すら呈する中受のリアルを追う。
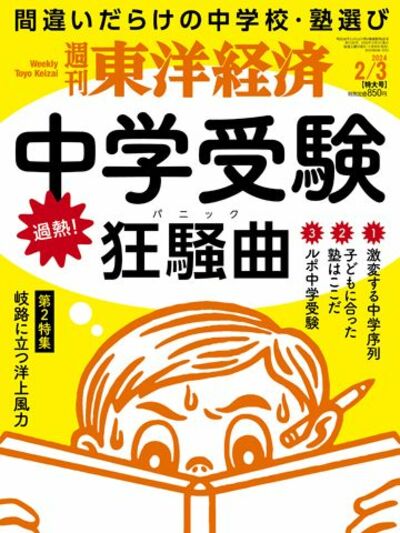
『週刊東洋経済 2024年2/3特大号(中学受験狂騒曲)[雑誌]』(東洋経済新報社)書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします。定期購読の申し込みはこちら
第1志望校と滑り止めの併願校、両校とも受かったら塾としてはどちらへの進学を勧めるか──全国300学習塾を対象にルートマップマガジン(以下、RMM)社が行っている「ダブル(W)合格調査」である。
第1志望の開成か、それとも併願校の早稲田大学や慶応大学の付属校(以下、早慶付属中)か、はたまた小石川中等教育か。「早慶付属中」「小石川中教」と回答した塾がともに初めて20%を超えた。依然として80%近くは「開成」と回答したわけだが、調査を始めた2018年に「早慶付属中」「小石川中教」と答えたのはわずか5%だった。5年間で塾の意識が大きく変わってきた。なぜか。
大学入試改革の衝撃
謎を解くカギは大学受験における「年内入試」だ。
トピックボードAD
有料会員限定記事

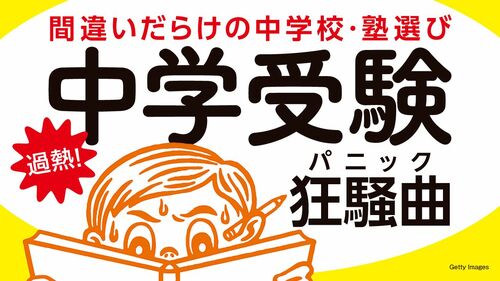































無料会員登録はこちら
ログインはこちら