首都圏中学校の偏差値は30年間でどう変化したか。

(写真:タカス / PIXTA)
何が何でも中高一貫校――。首都圏では小学校6年生の児童数が大きく減る中、中学校の受験者数が過去最多を更新しそうな勢いだ。なぜなのか。
『週刊東洋経済』2月3日号の第1特集は「過熱! 中学受験狂騒曲」。パニックの様相すら呈する中受のリアルを追う。
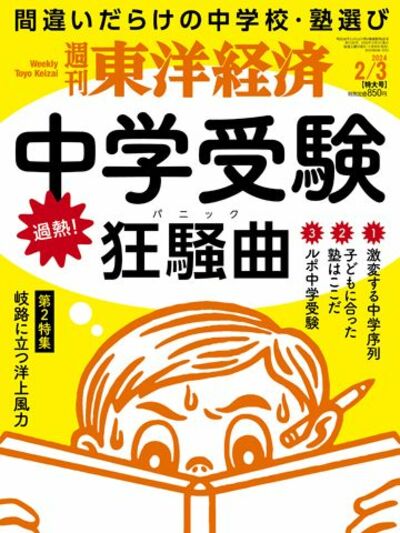
『週刊東洋経済 2024年2/3特大号(中学受験狂騒曲)[雑誌]』(東洋経済新報社)書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします。定期購読の申し込みはこちら
筆者は小学5年生の娘を来年、中学受験させるべきか検討中だ。自宅から通える範囲にどんな中学校があり、難易度はどうなのか。そう興味を持って調べる過程で、自身が小学生だった約30年前と偏差値の序列があまりに変化していることに驚いた。
実際に30年間で首都圏中学校の偏差値はどう変化したのか。首都圏模試センターの協力を得て、偏差値の上昇幅を男女別に並べたのが下の表である。
中学校には男女別の定員枠が残り、偏差値は性別で異なることが多い。30年前と同じ性別で比較できる学校を対象に集計したところ、とくに女子において偏差値が大幅に上昇した学校が目立った。
トピックボードAD
有料会員限定記事

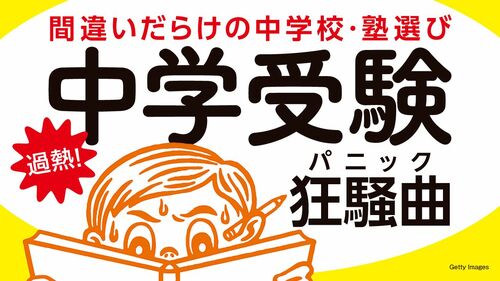

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら