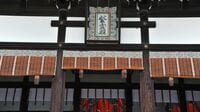「触れてはいけない存在」昭和天皇崩御が露わにした日本社会の構造
原 戦前もそうだったのではないか、と?
奥泉 そうなんです。そこがポイントです。じつは戦前も同じで、天皇と臣民という役柄構造のなかにのみ天皇崇拝はあった。それが私は言いたいのです。戦前戦中も天皇崇拝の構造は変わらなかった。
原 それはそうだと思います。同時代のドイツやイタリアと比較して、イデオロギーが希薄だった。
奥泉 中間層がアンチ天皇制になり、人々が関心を失ったように見えつつも、役柄構造に支えられた天皇の聖性はずっと持続していて、それが崩御のときに露呈した。
原 そうですね。戦前と戦後がつながっているというのは、宮内庁詰めになったときにもけっこう感じたことです。そもそも宮内庁の建物自体が戦前の宮内省とまったく同じ。あそこって本当に怖いんですよ。だいたい夜7時くらいに入るのだけれども、何もやることがない。そうするとあまりに退屈なので、ちょっと建物のなかを探検してみたことがあります。灯りが点いているのは記者クラブの部屋だけなのです。ひとたび部屋を出ると何があるかわからない。ましてや外は真っ暗闇で、非常に恐ろしい。だから皇居というのは、夜になるとそれ自体が禁域であるということがひしひしと身体に伝わってくる。
建築史家の藤森照信さんが、『建築探偵の冒険 東京篇』(ちくま文庫、1989年)のなかで皇居前広場に立ち込めている空気を「打ち消しのマイナスガス」と表現しましたが、そういう環境がタブーをつくり上げているという感じがすごくするのです。
奥泉 なるほど。
昭和の聖性、平成の聖性
奥泉 昭和から平成になりますね、そこでどう変化したか。同じように天皇の聖性、天皇の身体に対する不可触の感覚は持ち越されたと考えてよいのでしょうか。
原 ちょっとそれは違うような気がします。そもそも、身体が違うわけです。
奥泉 ええ、それは決定的ですね。