「マウントを取る道具」として広まる歪な論文信仰 専門家は「思考と責任」の便利な外注先ではない
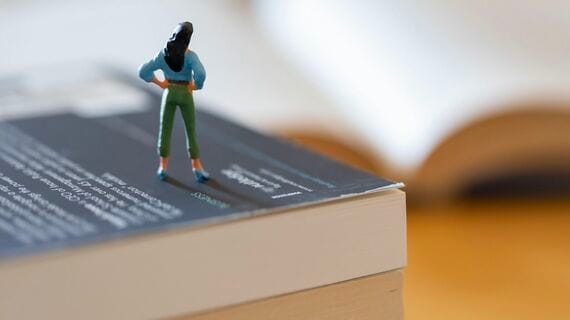
思考のアウトソーシングに使われる専門家
舟津:専門家の役割の1つとして、與那覇先生は「(専門が)異なる人どうしでも共有できる言葉を作ってゆくのが、正しい意味でのダイバーシティだ」ということをおっしゃっていました。まさにそのとおりだと思うのですが、改めてこの言葉の真意を伺えますか。
與那覇:ありがとうございます。私も以前は学者だったので、「専門性」が持つ価値を否定する気はまったくないんです。ただ、近年の日本では「専門家」という存在が、悪い意味でのアウトソーシングの道具になっている。ずっとそれを批判しているんですよ。
多くの読者や視聴者はいま、専門家に「考えること」をアウトソースしています。「専門家がこう言っているから、自分では調べなくていい。疑問を持たずに信じればいい」と。一方で彼らを起用するメディアにとっては、責任のアウトソーシングになっている。「専門家に出てもらった以上は、仮に中身がまちがっていてもその人のせいで、私たちは責任ないでしょ」というわけです。
最悪だったのはコロナで、対策のあり方がおかしいぞと気づいても、政治家は「専門家会議の結論に従っただけです」と言い訳する。ところが専門家は「決めるのは政治家の仕事。私たちは案を出しただけ」と言って、こちらも責任を取らない。
そうした状況こそを問題視しないといけないのに、コロナで感染症の専門家がコケても「いやいや、ウクライナ戦争の専門家は優秀だ」「統一教会問題の専門家は」「パレスチナ紛争の」……と居直り続け、同じ構図を繰り返している。そうした知の機能不全はなぜ起きるかと考えたとき、大学教員としての体験を思い出しました。
































