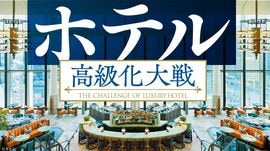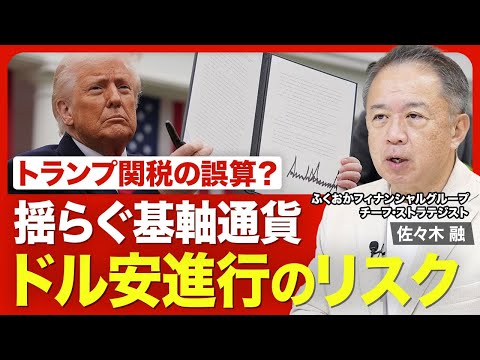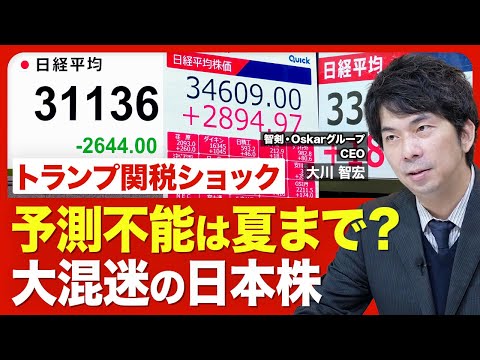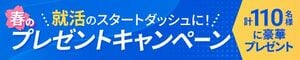「部下が勝手に育つ」上司が実践する"3つの方法" 育成力よりも「勝手に育つ仕組み」を強化しよう
また、このとき「スキル評価」の手順にコツがあります。
❷ 部下との1on1面談で、「自己評価」と「上司評価」をすり合わせる
❸ スキル項目のうち、何を身につけるかの「目標」を決める
❹ 全員の部下とすり合わせたら、一覧を「貼りだす」
❺ ◎と×・△を一緒に組ませて、仕事をしながら「教え合う環境」をつくる
この順番が大事です。
やってしまいがちな失敗が、部下に自己評価させず、上司がいきなり全スタッフの評価をすることです。
これでは意味がなくなってしまいます。
部下自身が自分をどう分析しているかが大事なことで、その自己分析の癖をつけてもらうことも、部下の成長にとっては欠かせないプロセスなのです。
部下がスキルの内容をよく理解しないまま、突然一覧を見せられ、自分の評価を勝手にされているとなると、何が起こると思いますか?
「私のこと、こんなにできないと思っていたんだ」とか、「私はできると思っているのに全然評価してくれない」と誤解が生まれ、上司と部下の信頼関係が壊れてしまいかねません。
最初に自己評価をさせることで、部下自身もスキル習熟度一覧に書かれているスキル内容を理解することができますし、自己評価をしたあと、その評価でいいのかどうかを1on1面談ですり合わせることで、さらに理解が進みます。
上司と部下の評価が一致したら、それを「目標」に変えましょう。
次はどの仕事を覚えたいか、いつまでにどのスキルを覚えるかなど部下自身の目標に変えることが重要です。
②ブラザー制度
2つめの仕組みは、ブラザー制度です。
ブラザー制度とは、スキルが未熟な人に教育係をつける制度のことです。
目新しくもない制度ですが、取り組めていない組織も多いです。
チーム内で仕事を教える人が、リーダーである自分しかいないとなると、部下育成は本当に大変になります。
ですので、部下が2人以上いるときは、ブラザーを決めましょう。
ブラザーになった部下は、仕事内容に教育係という役割を加えられたことになります。
このとき、部下2人のうち、ある仕事はAさんがブラザーでBさんが教わる立場、別の仕事はBさんがブラザーでAさんが教わる立場というように、仕事内容でブラザーと教わる立場を入れ替えるのも有効です。たとえば、2人とも新人だった場合は、AさんとBさんに対して、最初に覚えてもらう仕事を別にして、覚えた仕事をAさんとBさん同士で教え合うようにしてもいいでしょう。
このように、ブラザー制度は、教育係になってくれるということに大きな意味があります。
「教えることが最大の学びである」というように、ブラザーになった部下は、他の人に教えることを通して、大きな学びを得ます。ブラザー制度そのものが、教育係をも育てる仕組みにもなるのです。
では、肝心のブラザーは、どう決めるといいのでしょうか?